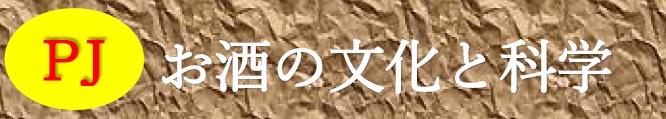

文京区の白山神社の境内にある関東松尾神社には、福島の蔵元、矢澤酒造店の「南郷」が奉納されています。
今さら言うまでなく、世界には多種多様なお酒があり、それぞれ国や地域に広まったお酒にまつわって、それぞれの酒の文化が築かれてきました。どんなお酒をどんな時にどのように飲むか―醸造技術や流通網の発達によって酒の大量生産が可能となり伝統的なスタイルは大きく変化してきたものの、その一方で、地元産の手作りの酒造りに注目が集まり、それを生業にしようと参入する若い人々の話もしょっちゅう耳にするようになりました。
この「お酒の文化と科学」プロジェクトでは、多様で奥の深い「お酒の世界」を、次のような切り口から探りを入れて、興味深い情報や活動を紹介し、「お酒とのよりよい(より深くて、より楽しくて、より健康的な)付き合い方」を見つけていきます。
1)酒についてこれまでにどんな研究がなされてきたのか、を大づかみにし、酒というものが(未知や未解決の問題を含めて)どんな多面的な存在であるかを、わかりやすい図解として提示してみる。
2)醸造学や発酵学の基礎的な知見を学びつつ、酒造りの現場を訪ね(そのためのツアーを組む)、取材をさせてもらって、生産者とツアー参加者との交流をはかる。それらを積み重ねて、日本の酒造りの現状を徐々に把握していく。
3)上記2つの事柄に取組むなかで、場合のよっては歴史や民族誌や先端的な技術や最新の医学的知見などにも踏み込んで、私たちにとって「お酒とのよりよい付き合い方」を考察していく。
ちょっと堅い表現になりましたが、メンバーはみなお酒が好きなので、時に杯を酌み交わしながら、この調査プロジェクトをすすめていきたいと思っています。
ご関心のある方はぜひご連絡ください。
ご連絡・お問い合わせはこちらから
プロジェクトメンバー:小野田美都江、谷俊一郎、石川求、森川浩司、上田昌文

<項目>
・韓国の自家醸造解禁の現在(2025-08-05)
・ノンアルコールビールあれこれ(2025-10-04)
*************************************
韓国の自家醸造解禁の現在
小野田美都江
1.日本における自家醸造禁止
日本では自分の飲むお酒を自宅等で醸すと酒税法違反になる。酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(酒税法第54条、第56条)ことになる。お酒とはアルコール度数1%以上の飲み物だと酒税法で定められている。したがって、世に「手づくりビールキット」なるものが売っているのは、発酵を1%未満で止めることが前提となっている。法律の範囲内で楽しむホビーである。
1980年代には前田俊彦による「ドブロク裁判」という酒税法に臨んだ裁判があった。「自分が飲む酒を自分でつくって何が悪いのだ」と前田は三里塚闘争ただ中の地でドブロクを醸し、国税庁長官に招待状を送って利き酒会を開催した。酒税法違反で起訴された前田は、酒税法は幸福権追求等を定めた憲法に違反する法律であると最高裁まで争ったが、有罪判決が確定する1)。日本で自家醸造を禁止する法律が施行されたのは1899(明治32)年1月1日からだ。以後、家で梅を焼酎等(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限る)に漬けて梅酒を作ることを許可する風穴が開いた以外、この規定は変わらないまま現在に至っている。
2.韓国の自家醸造禁止
韓国では日本の植民地時代以前は醸造制限が一切なく、自家醸造は各家庭に浸透していた。自家醸造される酒の種類は多様であり、マッコリはその1つにすぎない。マッコリ、マッカリ、マッコルリ(막걸리)と呼ばれる韓国の庶民のお酒は、「マツ=すべて、ひっくるめて、粗雑にざっと」「コルリ=漉す」という意味をもつ。マッコリは1回仕込みの速成酒(仕込後7日以内に飲める。単醸酒ともいう)のみならず、二醸酒、三醸酒…のように仕込み回数を増やして味を整えることが一般的である。家醸酒(カヤンジュ=家庭で醸造した酒)中心の韓国では、自家消費のための醸造に税金は課されず、自由な酒造りの家醸酒文化があった。そして、酒造りの担い手は女性である。
しかし、韓国統監府時代(1905[明治38]~1910[明治43])の1909[明治42] 年に「酒税法」が制定された。販売用、自家用に限らず酒造場毎に免許を申請し、税率軽微であるが納税が必要となった2)。1910[明治43]年、日韓併合となる。1916[大正5]年7月に朝鮮総督府は「酒税令」を発布し、9月1日より施行した。酒造に日本式の製法を推奨し、伝統的な醸造方法は日本式の米麹と酵母を使った製法へと代わることとなる。自家醸造は、朝鮮酒(伝統酒:濁酒[タクチュ]、薬酒[ヤッチュ]、焼酒[ソジュ])以外は禁止となる。ただし、朝鮮酒は造石数制限がなされた上、営業用より高めの税率が課された(鄭,2002)。
1945年に日本の敗戦により、朝鮮の植民地統治は終わり、大韓民国政府が樹立された。その後、1950年に朝鮮戦争が勃発し、1953年まで続いた。韓国は重篤な食糧不足に陥り、直ちに酒づくりが復活することはなかった。1964年、食糧難のため、米を使った酒の醸造が禁止される。酒の主原料にアメリカ産小麦粉が多用されるようになった。マッコリの味は大きく変わっていく。伝統的な濁酒類が作れない状態が続き、韓国伝統酒が次々と消えていった。人びとは、小麦粉マッコリの味に慣れてしまったという。1960年代は、焼酎(蒸留酒)製造も禁止され、希釈式焼酎(ソジュ)が普及し、低質で低廉な酒を大量に飲む文化が展開されることとなる。それは、1970年代まで続いた3)。
3.韓国の自家醸造解禁への道
朴正煕(パク・チョンヒ)が大統領に就任すると(在任期1963〜1979年)、糧穀節約汎国民運動を提唱し、1965年、米を使った酒醸造を禁じた。「雑穀類などで『代用マッコリ』がつくられ、工場でアセチレン製造の原料になるカーバイドを使って発酵させたマッコリが出回るようになる。『マッコリ=体に悪い、まずい』という悪評が定着し、『安いマッコリを飲むのは格好悪い』との固定観念も生まれた」とされる5)。しかし、次第に国内からも反発の声が起こり、米不足は続くものの、1978年から米のマッコリの醸造を認めた。伝統酒を保護・育成する方針を打ち出し、規制が次第に弱まっていった。そして1980年代、米の使用が徐々に解禁されたが、懐かしいマッコリの味を喜んだのは年配者であった。マッコリは時代遅れの酒の扱いであった。
1988年に開催されたソウルオリンピックによって、飲む酒の多様化(焼酎、ビール、ウィスキー、ワイン)が推進された。しかし一方で、ソウルオリンピック開催をきっかけに伝統文化を見直す機運も高まり、「民俗酒」という名で伝統酒への関心が強まった6)。そして、1988年、1991年と酒税法が改正された。米の消費量の減少への対応策として、米余り対策として米の酒類への使用が認められていった。同時に、地域復興策として小規模醸造場の設立条件も緩和され、酒造業の自由化政策が推進した。かくして、1995年の酒税法改正により、自己消費のみで販売しないという条件で、自家醸造が解禁となった。
4.花開く韓国の自家醸造文化
2009年、「韓国酒産業競争力強化策」を制定し、醸造所の設立要件がさらに緩和された。酒文化の復活に立ち上がった多くの団体や人物がある。例えば、韓国酒産業研究所(民間団体)が「マッコリ醸造塾(3カ月)」を開講した。「卒業生は2022年までに3000人以上。独立した人たちが韓国の各地に醸造所を建設。その数は、2021年に1000カ所まで拡大」7)した。韓国国内ではマッコリの高級化や味の改良が進み、美味しいマッコリが流通するようになった。2009年になると、健康指向や日本での韓流ブームによって、マッコリの需要が急増した。韓国のサムスン経済研究所の「2009年10大ヒット商品」アンケート調査(対象:同研究所ウェブサイトの会員1万1538人)では、53の候補商品の中から10商品ずつ選択する方法により、最高ヒット商品にはマッコリが選出された8)。マッコリ・ブームの到来である3)。これらは、伝統酒(マッコリ、薬酒=日本の清酒に近い酒)ブームと言い換えることもできる。
そして現在、「全国家醸酒(カヤンジュ)酒人選抜大会」や「大韓民国銘酒大賞」等、アマチュア醸造家が醸した自家醸造酒のコンクールが開催されている。地区予選から全国大会へと選ばれていく大きな大会である。老若男女の多くの作り手が参入している。各地の自家醸造所を巡るツアーも盛んである。自家醸造解禁が韓国に新たな酒文化を創出していることが見て取れる。この伝統酒ブームのムーブメントを支える多くが、進取の精神に富んだ若い人びとである。
以上のように駆け足で韓国の伝統酒ブームの経緯をみてきた。この状況について、大手酒造企業や業界団体の反応や、国税収入への影響等については調べ切れておらず、今後の課題として調査研究を継続していく予定である。
【謝辞】本稿については、筆者と共に日韓酒文化研究会を主宰する韓国在住のメディア人類学者、金ヨニ(金暻和)先生からも多くの示唆をいただいた。
1) 前田俊彦編著, 1986, 『ええじゃないかドブロク』三一書房.
2) 朝鮮酒造協会編, 1935, 『朝鮮酒造史』朝鮮酒造協会.
3) 許時銘, 2010, 「暮らし 2009年韓国で起きたマッコリ・ブーム」『Koreana : 韓国の文化と芸術』17(1), 86-90.
4) 鄭大聲, 2002,「伝統酒マッコルリのつくり方とその文化」『日本醸造協会誌』97(4), 265-274.
5) 朝日新聞2009年12月09日13頁「(世界発2009)生マッコリ、韓国夢中 女性・若者『お肌にいい』『飲みやすい』」
6) 白珍尚, 2006「韓国酒類産業の構造変化におけるマーケティングとイノベーション」
『流通』19, p. 39-45.
7) 日本経済新聞2022年5月31日「マッコリ醸造塾」受講3年待ち 韓国伝統酒に新風(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM306CI0Q2A530C2000000/)
東京新聞2021年10月25日「韓国でマッコリや清酒、焼酎など伝統酒が復権 20~30代が支持、酒づくりの担い手も若者 」https://www.tokyo-np.co.jp/article/138750
8) Wow Korea, 2009.12.17, https://www.wowkorea.jp/news/read/065647.html (2025年7月23日アクセス)
ノンアルコールビールあれこれ
森川浩司
「お酒の文化と科学プロジェクト」ですが、いやだからこそ、お酒の”周り”の話題も扱います。今回はノンアルコール飲料、特にノンアルコールビールについてのお話です。
ノンアルコールビールを飲む
2025年7月26日に市民科学研究室の事務所にて、ノンアルコールビールの試飲会を行いました。「お酒の文化と科学プロジェクト」メンバーが各自お薦めのノンアルコールビール(と、アルコールの入っていない飲み物は飲み物ではないというメンバーは低アルコールビール)を持ち寄って、試飲会参加者みんなで飲み比べしてみようという会でした。
当日は、ノンアルコールビールってこんなに種類があるのか!とびっくりするくらい、日本製・海外製のノンアルコールビールが揃いました。私が持参したうちのひとつはアサヒビール株式会社(以下アサヒ)の「アサヒゼロ」。これを最初に飲んだ時は衝撃的で、「これはビールじゃないか!」と思ったのを覚えています。20年以上前にもノンアルコールビールを飲んだことがありますが、当時は種類は少なく、また飲んでみても「これはビールの感じがまったくしないなぁ」と思った記憶がありますが、今回はあまりにもビールっぽかったからか、アルコール0.00%なのに軽く酔ったような感じがしました。運転するからノンアルコールビールを飲む、という場合があると思いますが、軽く酔ったような感じがするけどアルコール検査では反応なしとなるのかどうか気になったくらいです。
そんなノンアルコールビール試飲会については〇〇さんによるレポートがありますので、詳しくはぜひそちらを読んでいただければと思います。
ノンアルコールビール調査を読む
広がりと深まりを感じさせるノンアルコールビール。それに呼応してノンアルコール市場に関する調査も複数出てきています。ここではサントリー株式会社(以降、サントリー)と麒麟麦酒株式会社(以降、キリン)による2024年の調査を比較しながら見てみたいと思います。(参考文献の欄にリンクを載せています。)
- 調査の概要
サントリーの調査対象は、一都三県(東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県)に在住する20~60代の男女30,000人のうち、ノンアルコールビールテイスト飲料(以降、ノンアルコールビール)の月1日以上飲用者1,238人。
キリンの調査対象は全国の20-59歳男女960名(学生除く)。
どちらもインターネットでの調査です。 - 市場規模
サントリーの推定によると、ノンアルコールビールの市場はこのところ頭打ち傾向ですが、ビールテイスト以外(チューハイテイストやワインテイストなど)が伸びている影響で、ノンアルコール飲料全体としては市場規模は年々少しずつ拡大しています。
2021年にやや大きな拡大がみられていて、これについてのサントリーのコメントは特に見当たりませんが、インターネットで調べてみると、コロナ禍による家飲みが増えて健康に気を使ってノンアルコール飲料の消費が増えたのではないかという推測をみつけました。
スーパーマーケットのお酒コーナーに行くと、ノンアルコール飲料はノンアルコールビールの他にいろいろな種類のものがたくさんあって、売り場スペースもそれなりに大きく、市場の拡大を実感できます。 - ノンアルコール飲料の飲用経験
サントリーの調査でもキリンの調査でも、ノンアルコール飲料を飲んだことのある人は調査対象の半分弱で、飲んだことのある人の中の約8割くらいはノンアルコールビールを飲んだことがあるようです。
サントリーはここ何年か同じ内容のノンアルコール飲料の調査をやっているようで、2023年の調査との比較があり、1年以内に飲んだことのあるノンアルコール飲料の中でノンアルコールビールは約8割で変化はありませんが、ノンアルコールワインテイストやノンアルコールカクテルテイスト、そしてノンアルコール焼酎テイストの割合が増えています。
私もノンアルコールワインテイスト飲料を飲んでみました。ワインからはだいぶ遠い感じがしましたが、どうせノンアルコールならと葡萄ジュースを飲むよりもノンアルコールワインテイスト飲料の方がワインの代替にはなるのだろうなと思いました。 - ノンアルコール飲料の飲用シーン・飲用理由
サントリーの調査でもキリンの調査でも、どういうときにノンアルコール飲料を飲むか、その飲用シーンについての項目があり、どちらもアルコールが飲めない場面で代替品として飲まれていることがうかがえます。
サントリーの調査には世代別の回答も載っており、20代は「夕食後」「昼食時」「休日の昼間」「料理をしながら」という場面での飲用比率が他の世代よりも多くなっています。若い人はアルコールの代替品として以上にノンアルコール飲料に親しんでいる感じがしますね。
また飲用理由については、アルコールが飲めない状況の他に、健康面から(例えば休肝日の飲み物として)飲まれたりしているようです。加えて、リフレッシュ・気分転換という理由もそれなりに割合が高く、ノンアルコール飲料にはアルコールの代替品という以上の役割もありそうです。 - こんな場面でノンアルコール飲料はOK?NG?
キリンの調査では、ノンアルコール飲料を飲むことに対する抵抗感の有無をシーン別に尋ねています。個人的にはこの結果がいちばん面白かったです。
就業時間中の飲食店での一人ランチ・同僚とのランチ、オフィス内でのランチ、オフィスの自席、仕事の会議中に、いくらアルコール0.00%だからとはいえノンアルコール飲料を飲むのは是か非か?あなたならどれはOKでどれはNGでしょうか?
どんな結果が出たか、興味ある方はぜひキリンの調査結果をご覧ください。
昔のノンアルコールビールは、ビールを飲みたいけれど今は飲めないからしかたなく代替品として飲む飲み物という位置づけだったと思いますが、今は健康志向もあって体にいい成分が入ったいわゆる機能性飲料の側面を持つものもあり、積極的にノンアルコール飲料を飲む・楽しむというように変わってきている印象です。
考えてみれば、食事にあわせるノンアルコール飲料の選択肢は実は今まであまりなかったのかもしれません。クラフトコーラがブームですが、そんな風に、ノンアルコールビールに限らず食事に合わせて楽しむノンアルコール飲料のクラフトものがどんどん出てくる可能性も考えられます。アルコールが飲みたいけど飲めないから、ではなく、気分やシーンに合わせてアルコールやノンアルコールを自在に切り替えて楽しむ、いろんなアルコール飲料があるようにいろんなノンアルコール飲料を飲み分ける、そんな時代が来ているのかもしれません。
私が「これはビールじゃないか!」と思ったアサヒの「アサヒゼロ」は、濃厚なビールを醸造してからアルコール分を完全に取り除くという製法で作られているそうです。これと同様にラガータイプのビールを醸造してからアルコール分を完全に取り除くという製法で作られた「ラガーゼロ」がキリンから発売になりました。飲んでみたところ、「アサヒゼロ」ほどの衝撃はありませんでしたがこれまた確かにかなりビールっぽく、そしてまたまた飲んだ後少し酔っている感じがしました。
ビール・発泡酒・第3のビール(新ジャンル)などビール系飲料の酒税が2026年10月から統一されますが、サントリーが第3のビールのヒット商品「金麦」をビール化することを2025年9月末に発表しました。そのサントリーはまだアサヒの「アサヒゼロ」やキリンの「ラガーゼロ」のような商品は発売していません。ビール系飲料の酒税統一でビールが盛り上がりそうですが、ノンアルコールビールも同様に盛り上がりそうで、季節はすっかり秋になりましたがビールもノンアルコールビールも(そしてその他のノンアルコール飲料も)これからますますアツくなりそうです。
参考文献
麒麟麦酒株式会社, 2024, ノンアルコール飲料意識調査2024【グリーンズフリージャーナル】
サントリー株式会社, 2024, ノンアルコール飲料に関する消費者飲用実態・意識調査 サントリー ノンアルコール飲料レポート2024
