『市民研通信』定期コラム 「トピック・ミニ解説」03_第83号掲載分
007_二本松から考える、有機農業と風景の未来
毛利公美(市民科学研究室会員・食の総合科学研究会メンバー)
2025年12月20日
PDFファイルはこちらから
二本松から世界を眺める
東京から270キロほど離れた福島県二本松市の岩代地区は、山あいの斜面に切り拓かれた小さな農地が点在する、いわゆる中山間地である。私がここに足しげく通うようになったのは、東日本大震災の後、被災した有機農家を支えたいという思いから日本有機農業研究会が行っていた「猫の手」援農に参加したのがきっかけだった。そこで知り合った有機農家さんとなぜかうまがあい、手伝いと称してたびたび遊びに行って、だんだん家族同然の付き合いをするようになると、大都会東京で暮らしていると見えないさまざまな問題が見えてきた。
少子高齢化の問題は、地方の小さな農村では過疎化や後継者不足による農地の荒廃へとつながる。昨年からの「米騒動」も、都会の消費者にとっては第一に「価格の問題」として捉えられるが、その根底にあるのは、担い手不足によるこれからの日本の農や食糧問題の危機という、より深刻な問題だ。農林水産省の報告によれば、2000年には約240万人いた基幹的農業従事者は、2024年には約111万4千人まで半減した。さらに、若い世代の割合は非常に低く、基幹的農業従事者のうち49歳以下は約11.2%しかおらず、65歳以上が約71.7%を占め、平均年齢は約69.2歳に達しているという統計がある[1]。これは農業生産者の数だが、そもそも田舎には若い人が少ない。子どもがいない。子どもがいても、農業をやりたがらない。
市民研がプロジェクトとして掲げている活動の一つに、「廃校有効活用(二本松市)」[2]があるが、今年の春で廃校になった福島県立安達東高等学校には専門系列の一つとして農業コースがあり、校内には実習のための広い畑や大きな温室、加工の技術が学べる調理実習室、植物バイオテクノロジーが学べる農業実験室などのさまざまな設備や農業機械が備わっていた。市民研のプロジェクトは、それらを活用して農業研修施設や地域活性につながる施設を作れないかという地域住民の声を受けて始まった。2024年10月24日には、二本松市の公民館の会議室で、福島県立安達東高等学校の有効活用の道を探るための市民ワークショップが開催された。地元側のコーディネータの方に声をかけてもらい、東京から日帰りで参加したのが、私の市民研との出会いだった。
帰りの新幹線の中では、代表の上田さんから市民研の取組みについてお聞きし、有機農業や食をめぐる問題について語り合った。「食の総合科学研究会」では毎月一度、読書会をオンラインで開いているが、その時の課題図書だった真田純子著『風景をつくるごはん』(2023年、農文協)は、私自身、別の読書会でちょうど読んでいるところだった。科学とは無縁な人生を送ってきた私が市民研の会員になったのは、こういういくつかのめぐりあわせに導かれてのことだった。
風景がつくるご飯
真田純子氏の著書『風景をつくるごはん』には「都市と農村の真に幸せな関係とは」という副題がついている。この本は、農業や農村を「守るべき対象」として語るのではなく、都市と農村がどのような関係を結び直せるのかを考えるための思考の足場を提供している。「食べること」と「農村の風景」を切り離してきた私たちのものの見方そのものを問い直す本だと言ってもいい。
著者は、農業や食を経済や生産性の問題としてではなく、人の営みが積み重なって現れる「風景」として捉えるところから議論を始める。本書で繰り返し示されるのは、農村風景とは自然に「残っている」ものではなく、日々の農作業や暮らし、地域の人間関係、そして外部からの政策や市場の力が絡み合って形づくられてきた結果だという視点である。美しい棚田や里山の風景は、観光資源でもノスタルジーでもなく、農業が続いてきた痕跡そのものだと位置づけられる。
真田はここで、都市に暮らす消費者の食の選択が、実はこの風景の存続と深く結びついていることを明らかにする。安さや利便性だけを基準にした食の選択は、結果として農村の負担を増やし、農地の荒廃や集落の消失につながってきた。一方で、どのような作物を、どのような価格で、どのような関係のもとで買うのかという選択は、農業のやり方だけでなく、その地域の風景そのものを方向づける力を持っているというのだ。
また、本書の大きな特徴は、日本の状況を閉じた問題として扱わず、ヨーロッパ、とりわけEU諸国の農業政策や景観政策との比較を通じて考察を深めている点にある。EUでは、農業は単に食料を生産する産業ではなく、環境や景観、地域社会を維持する公共的な営みとして位置づけられ、それに応じた支援が制度化されてきた。著者は、こうした事例を紹介しながら、日本ではなぜ「風景を守る農業」が制度的に支えられてこなかったのかを問い直す。
同時に本書は、単純に「ヨーロッパを見習えばよい」とは言わない。日本の農村が歩んできた近代化の過程、工業化と都市集中の中で農業が担わされてきた役割を丁寧にたどりながら、都市が豊かになる代わりに、農村が引き受けてきた見えないコストに目を向ける。そのうえで、農村の問題を「地方の問題」「農家の問題」として切り離すのではなく、都市に暮らす人びとの生活と地続きの問題として捉え直す必要性を示している。
終盤で提示されるのは、大きな改革案や理想論ではない。むしろ、日々の食卓や買い物といった、ごく身近な行為が、農業のあり方や風景の未来とどのようにつながっているのかを考える視点である。「風景をつくるごはん」というタイトルが示す通り、私たちはすでに、食べることを通して風景づくりに参加しているのだ、という気づきが、静かに読者に手渡される。
この本が提案する「都市と農村の真に幸せな関係」は、実は、有機農業がそもそも目指していた根底にある価値観そのものでもある。
有機農業という言葉が問い続けてきたもの
「有機農業」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、体にやさしそうな野菜や、環境に配慮した暮らし、そして少し高価な食べものかもしれない。健康志向の人や、余裕のある人が選ぶもの、というイメージも根強い。そうした理解は、決して的外れではないが、それだけでは、有機農業が日本社会の中で果たしてきた役割の大部分が見えなくなってしまう。
いま、日本の農業は、深刻な転換点にある。生産者の高齢化が進み、リタイアが相次ぎ、後継者が見つからないまま農地が手放されていく。米をはじめとする農産物の価格は長く低迷し、作れば作るほど生活が苦しくなるという矛盾が放置されてきた。その結果、農業が「続かなくなる」こと自体が、現実の問題として立ち現れている。
この状況を、感情論や危機感だけで語るのではなく、冷静に捉えようとする試みも存在する。過去の統計データから、生産者がどの段階で農業をやめていくのかを確率的に推計し、その傾向が続いた場合の将来像を描く研究である。こうしたモデルは、担い手減少が単なる印象ではなく、構造的な現象であることを示している。
しかし同時に、こうした推計には限界がある。モデルが扱えるのは、年齢や経営規模、所得といった数値化できる要素に限られる。なぜその人が農業を続けてきたのか、何に支えられて踏みとどまっているのか、あるいはどんな関係の中で農を営んできたのかといったことは、ほとんど反映されない。数字は重要だが、数字だけでは見えない現実もまた確かに存在する。統計データはどんな危機的な数値も無味乾燥な数字でしかないが、その背景には、実際にそこで暮らす人々の想いがあり、鮮やかな「風景」があるのだ。
ここで、有機農業の歴史を振り返る意味が立ち上がってくる。有機農業は、しばしば「農薬や化学肥料を使わない農業」と説明されるが、それは結果の一部にすぎない。日本で有機農業が語られ始めた当初、それは技術の選択というよりも、社会のあり方への問いだった。
高度経済成長期、公害や農薬被害が深刻化する中で、有機農業に関わった第一世代の人びとは、単に安全な作物を作ろうとしたのではなかった。効率や競争、拝金主義を前提とする近代的な市場社会に対して、人と自然、人と人が切り離されずに結びつく別の世界を思い描いていた。生産者と消費者が対等な関係でつながり、誰かの犠牲の上に成り立つ豊かさではなく、みんなが納得して生きられる社会を目指す。その思想を表す言葉として選ばれたのが、「有機」という語だった。
「有機農業」という言葉は、特定の誰かが名付けたものではない。1960年代末から70年代初頭にかけて、農業の近代化や農薬多用への違和感を共有した農業者・消費者・研究者たちが、農業の技術だけでなく社会との関係そのものを問い直す言葉として、意識的に選び取り、使い始めたものである。中心となったのが、冒頭で「猫の手援農」の主催者として名前を挙げた日本有機農業研究会だ。1971年に創設されて以来、一貫して農の問題を社会問題と捉え、有機的な農業こそが閉塞した今の世の中を変える「世直し運動」につながる営みだと訴えてきた。
商品化する有機農産物、生き方としてのオーガニック
その後、有機農業は時代によって姿を変えていく。1980年代になると、社会は安定し、人びとの生活は忙しくなる。都市化や共働き世帯の増加により、消費者が生産者と直接関係を維持することが次第に難しくなった一方で、「安全で質の高い食」を求める需要自体は定着していった。この流れの中で、有機農産物を商品として扱い、安定的に供給する宅配業者やオーガニック専門店が登場する。ラディッシュボーヤのような事業者は、その代表例である。お金さえ払えば毎週届く野菜セットは、生活を変えすぎることなく、有機農業とつながる手段だった。この段階で、有機農業は運動からビジネスへと姿を変えたのだ。そして、次第に規格や認証が整えられ、2000年には有機JAS制度が始まる。有機農産物は広く流通するようになったが、その一方で、「有機が高級品になってしまった」「理念が見えにくくなった」という違和感も生まれた。有機農業は「裕福で意識の高い人のもの」というイメージを帯び、社会運動の文脈から切り離され、市場を通じて拡大可能なモデルとして再編されていった。
1990年代後半以降、バブルが崩壊し、経済成長が当たり前ではなくなると、将来への不安が広がるなかで、人びとは「どんな豊かさを選ぶのか」を問い直し始めた。経済成長や大量消費を前提とした「豊かさ」に疑問が投げかけられるようになり、環境問題や持続可能性への関心が高まると、有機農業は新たな意味を帯びるようになった。都会での生活ではなく、地方に移住して小さな畑を始める若者や、農業を副業として取り入れる都市生活者も増加し、さらにコロナ禍による価値観やライフスタイルの変化がそこに拍車をかける。彼らは必ずしも「有機JAS」にこだわらない。自然栽培、在来種、自給的農業。キーワードは多様で、共通しているのは「これは自分の生き方の問題だ」という感覚である。彼らにとっての有機農業は、社会運動でも、拡大を目指す産業でもなく、個人の倫理や美意識に根ざした実践となる。これは、担い手減少をめぐる議論の中で、しばしばモデルからこぼれ落ちる選択でもある。
子どもたちに安全な食べ物を食べさせたいと思うお母さんたちが中心となって起こした「オーガニック給食」運動も、少しずつ広まってきている。第一世代の有機農業が掲げた「世直し」の理想を引き継いだ運動ではないが、子どもの食や地域の農業という具体的な場面において、有機農業が問い続けてきた価値の一部を、制度の内側で実装しようとする試みだと評価することはできる。
「みどり戦略」の理想と現実
こうしたなか、2021年に農林水産省は農業・食料・農村を環境配慮型へ転換していくための長期戦略として、「みどりの食料システム戦略」を打ち出した。この戦略の柱は、温室効果ガスの削減や生物多様性の保全といった環境目標を、技術革新と生産性向上によって同時に達成することにある。具体的には、化学農薬・化学肥料の使用削減、有機農業の面積拡大、スマート農業やデジタル技術の導入、脱炭素型の生産・流通体系の構築などが掲げられ、環境に配慮しつつ「強い農業」をつくることが目標とされている。これは、表向きには、環境と経済を両立させる前向きな戦略に見える。
だが、一方で、国の農政には、以前から一貫して、農地の集積・集約、経営体の大型化、少数の担い手への集中を進める方針が存在する。ここで想定されている担い手像は、資本力があって技術投資が可能な大規模な業者であり、農業を効率的な産業として成立させることが前提になっている。大規模農業は平野部や条件の良い農地では一定の合理性を持つが、地形が複雑で農地が分散しており、高齢者が多い中山間地では、そもそも成立しにくいのだ。
また、みどり戦略における有機農業は、農薬・化学肥料を減らし、環境負荷を下げる技術として位置づけられる傾向が強い。その結果、生産者と消費者の関係や地域の集落の維持といった、第一世代の有機農業が重視してきた社会的・関係的な側面が抜け落ちている。
国の戦略は「少数精鋭の担い手で、効率よく支える農業」を描いているが、現実にはその「少数精鋭」自体が急速に高齢化し、減少している。結果として、担い手が減っている問題を、担い手をさらに絞ることで解決しようとしているという矛盾が生じているのだ。それに、農業は単に食料を生産するだけでなく、里山の管理、水路や農道の維持、集落のつながりといった、地域そのものを支える役割も果たしてきた。大型化・効率化を前提にすると、これらの役割は「非効率」として切り捨てられやすく、結果的に、農村の弱体化や自然環境の荒廃を招く可能性がある。
豊かな土や自然をとりもどすために
『広辞苑』によれば、「有機」とは「①生物体を構成する要素であること。生命にかかわること。②部分が相互に関連し、全体として統一や働きをもつこと」とある。「有機農業」という言葉が選ばれた背景には、農薬や肥料の問題にとどまらず、農と社会の関係そのものを問い直そうとする意図があったことはすでに述べたが、問い直すべきは、「農と社会」「生産者と消費者」の関係だけではない。「自然と人間」「土と作物」これらが切り離されず、循環し、関係として成り立っている状態が理想である。
有機農業は「農薬や化学肥料を使わない農業」と位置付けられることが多いが、実際は、有機農業と一口に言っても、その土地の風土や特徴、個人の考え方によって、さまざまなやり方がある。昨今ではたい肥などの有機肥料さえ使わない自然栽培や、土を耕さずに植物や微生物の力を借りて作物を育てる不耕起栽培が注目されている。とりわけ後者は、耕起によって壊されてきた土壌の構造や微生物の働きを、人為的に管理する対象ではなく、時間をかけて育まれる関係として捉え直し、人が土を「作る」のではなく、土が自ら回復し、循環する力を引き出す農法であり、その結果として、環境負荷を抑え、長期的に持続する農の形を目指している。
市民研の「食の総合科学研究会」でも、『風景をつくるご飯』の後、読書会の課題本として、金子信博・元福島大学教授が書かれた『ミミズの農業改革』(2023年、みすず書房)を読んだ。『ミミズの農業改革』は、ミミズに象徴される土壌生態系の働きを軸に、人が自然を管理する農業から、自然の循環に委ねる農業へと発想を転換する必要性を説いた本だ。金子先生は福島で不耕起栽培の畑を実践していらっしゃった経緯があり、私が通っている二本松の有機農家とのつながりも深い。私自身、金子先生の講演や本をきっかけに、不耕起栽培の魅力や土の中の豊かな世界に大きく引き込まれた。
土壌についての「科学的な」知識の裏付けをきちんと得たいという気持ちから、次の課題本は土壌微生物学に関する入門的解説書『エッセンシャル土壌微生物学 作物生産のための基礎』(2021年、講談社)が選ばれたのだが、生物学や地学については中学レベルの知識さえおぼつかない、典型的文系人間には、なかなか読みこなすのが難しい。
土の中の豊かな世界や有機農業の多様な展開については、これから一生かけて学んでいきたいと思っている。皆さんにもぜひ、この豊かな世界を一緒に探検していただきたい。なぜなら、私たちはみな、生き物として有機的につながっているのだから。
[1] 農林水産省「令和6年度食料・農業・農村白書 第1部 食料・農業・農村の動向 第2章 農業の持続的な発展 第3節 担い手の育成・確保と多様な農業者による農業生産活動」https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/r6_h/trend/part1/chap3/c3_3_00.html
[2] https://www.shiminkagaku.org/nihonmatsupj/

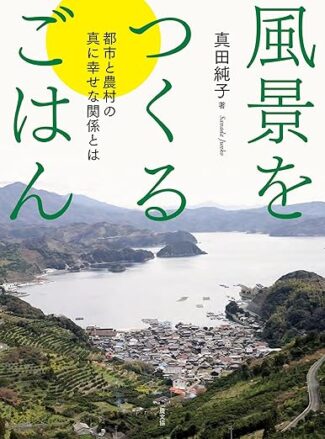
有機農業は社会のあり方への問いであり、生き方の問題であり、土の中の豊かな世界から育っているとの解説に共感しました。二本松からですから、今後、放射能に伴う被害や汚染、その対処についても知りたいと思いました。