エッセー・レビュー
『山本義隆自選論集(Ⅰ)物理学の誕生、(Ⅱ)物理学の発展』を読む
猪野修治(湘南科学史懇話会・代表)
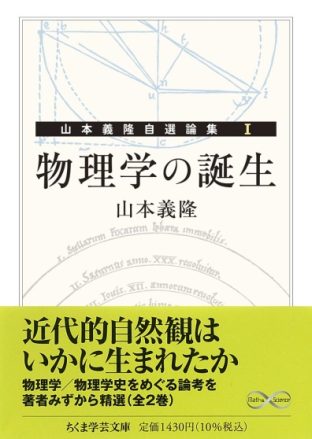
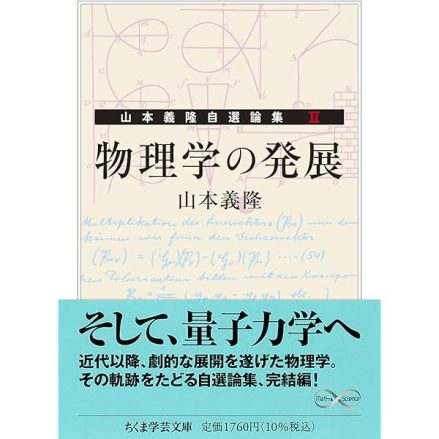
『物理学の誕生 山本義隆自選論集Ⅰ』 『物理学の発展 山本義隆自選論集Ⅱ』
(ちくま学芸文庫、2024) (ちくま学芸文庫、2025)
PDFはこちらから
Ⅰ はじめに
山本義隆氏(物理学・科学史)が昨年から今年にかけ、これまでの多数の重厚な既刊の単行書の構成とは全く異なる前例のない構成の「自選論集」を上梓・刊行した。それが『物理学の誕生 山本義隆自選論集 Ⅰ』と『物理学の発展 山本義隆自選論集 Ⅱ』である。前者には11本の論考、後者には12本の論考が収録されている。種々の雑誌や書籍の編集部から依頼され寄稿したものだ。それらのほとんどは物理学と科学史にかんする論考である。
それでも、あえて大きなメイン・テーマは何かと言うと、前者は「16世紀文化革命」(大佛次郎賞受賞講演)と「物理学の誕生」(大阪府立大手前高校講演)であり、後者は「相対性理論入門講座」(駿台予備学校講演)である。その他は非常に短いものから長いものまで、多種多様な論考である。それらのすべての論考を取り上げた。いずれも読み学び応え十分の論考ばかりであり、著者ならではの独創的な論述の展開に目を見張り唸る思いで読んだ。
このエッセー・レビュ―では、それらの長短合わせ23本のすべての論考を遡上に挙げ紹介する。そのさい、著者自身の言葉を重視し、それらは「 」で示し頁を明示した。それがないものは私の文章である。そのさい、前後の文脈がないと理解できない言葉もあるかとも思うが、そこは読者の想像力に委ねたい。しかし現物を手に取り眺めれば一目瞭然である。では始めましょう。
Ⅱ 山本義隆『物理学の誕生』
本書は11本の論考から構成されている。
1 アリストテレスと占星術
これは、通常は見られない視点であるが、西欧中世社会への占星術の浸透は、アリストテレスぬきには語れないことを論述したものである。
2 近代的自然観の形成―発展のカギとなった遠隔力の概念
アリストテレスの二元的世界から、コペルニクス、ガリレイ、デカルト、ティコ・ブラーエ、ギルバート、ケプラーをへて、ニュートンによって完成される天文学の歴史が完結に論述されている。ここでの議論の根本的なカギは「遠隔力」であることを論述する。
主要な項目は次のようである。
1 輝かしい発展の歴史も調べてみれば、数々の誤解と見当違いの繰り返し
2 コペルニクスの遅動説 その到達点と限界
3 ギリシャの知恵はイスラムに ヨーロッパの学問は12世紀から
4 アリストテレスの二元的世界 地球の絶対的静止
5 大航海時代の経験とヨーロパ人の意識の変化
6 揺らぐ「不安の天空世界」 超新星の出現が引き金に
7 ケプラーの出発点 聖職者への道から天文学へ
8 火星だから発見できた「楕円」軌道 第5元素の常識にピリオド
9 「地球は磁石」を太陽に拡大解釈 それが動的天文学への転換点に
10 力の概念をめぐって 機械論の二つの立場
11 イギリスにおける実験哲学 遠隔力の容認
12 発見の下地は錬金術にある? ニュートンと遠隔力
13 万有引力概念の勝利 物理学の目的とは
3 在野で学ぶということについて。付録》第一級のノンフィクション、大佛次郎『パリ燃ゆ』の面白さ
著者は第30回大仏次郎賞を受賞しているが、その大佛次郎の名著『パリ燃ゆ』こそは、ノンフィクションの第一級の面白い作品だと称賛した論考である。著者は大佛の執筆姿勢にあやかりたいと思ったに違いない。
「本書は、ルイ・ボナパルトによるクーデターから普仏戦争における帝政の崩壊、そして国防政府の裏切りに対するパリ労働者の自然発生的蜂起とパリ・コンミューンの成立から敗北までを詳細に描いたもので、日本語で読めるパリ・コンミューンについての書物の中で類比を絶せるものであり、おそらく外国でもこれだけのものはないのではないか」(本書、p.54)
4 『磁力と重力の発見』をめぐって
あの名著『磁力と重力の発見』が大佛次郎賞を得たさい、この本は、理系書と文系書とか、専門学術書と一般教書とか、の区別を拒否し、なによりも、誰の批判にも耐える面白い書であることを目指したことが記されている。「書物はひとたび市場に出たならば、産みの親である著者の手を離れ、一人歩きを始めます。本書が今後、どのような運営をたどるのかはわかりませんが、著者としてはひとりでも多くの読者にできるだけ愛されてほしいと願っております」(本書、p.60)
5 16世紀文化革命
「16世紀文化革命」とは著者の造語である。主要な内容は、16世紀に何が起きたのか、蔑視されてきた職人たち、職人が本を書き出した、知の世界を支配していた古代信仰、大航海時代がもらした衝撃、民衆の学問を阻んだラテン語の壁、俗語の使用が学問を開放する、秘匿された知から公開の知へ、というものだ。16世紀には大学や教会の外で、さまざまな職人たちの活動があり、そのいわば隠れた活動が17世紀の科学革命の礎になったというのが、著者のいう「16世紀文化革命」の提唱なのである。
主要な項目は次のようである。
1 16世紀に何が起きたのか
2 蔑視されてきた職人たち
3 職人が本を書き出した
4 知の世界を支配していた古代信仰
5 大航海時代がもたらした衝撃
6 民衆の学問を阻んだラテン語の謎
7 俗語の使用が学問を開放する
8 秘匿された知から公開の知へ
6 「ルネサンス」と「16世紀文化革命」
「こうして16世紀の職人たちは、ラテン語の壁で守られていた小数の聖職者やエリート知識人による知の独占に風穴をかけ、職人の手仕事を卑しいものと見る古代以来の偏見を掘り崩し、道具を使い装置を組み立ててする実験の有効性と重要性を突き出し、古代以来の文書偏重の学から経験重視の知への転換を促していた。それは17世紀の科学革命を準備する知の世界の大規模な地殻変動であり、「文化革命」と規定するのに十分値する」(本書、p.098)
7 科学史の基本問題に取り組んで
箸者は西欧科学誕生史の三部作『磁力と重力の発見』『一六世紀文化革命』『世界の見方の転換』を上梓している。その後、その補完物して上梓した著書『小数と対数の発見』が、2020年度日本数学会出版賞を受賞した。そのさいの受賞者のことばである。
8 シモン・ステヴィンと16世紀文化革命
16世紀中頃のオランダに生きたシモン・ステヴィン(1548-1620)という科学者(数学者、技術者、自然科学者)がいる。本稿はそのシモン・ステヴィンの科学者としての仕事を詳細に紹介するものだが、あのガリレイをもしのぐ先見性をもっていたこと、つまりステヴィンは17世紀科学革命の先駆者であった、ことが論証される。
主要な項目は次のようである。
はじめに
1 オランダ人シモン・ステヴィン
2 科学における俗語の使用をめぐって
3 ステヴィンとフランシス・ベーコン
4 ヨーロッパ各国における俗語使用の登場
5 16世紀文化革命
9 「ガリレイ革命」をめぐって
「私は、ガリレイこそ最初の近代人、少なくとも最初の近代科学者だと思っている。ガリレイこそは―正にも負にも―近代科学精神の体現者なのだ。じっさい近代物理学―ひいては近代自然科学―の創設者を一人だけ挙げよといわれれば、やはりガリレイということになるだろう。ガリレイは革命を起こしたのだ」(本書、p.141)
主要な項目は次のようである。
Ⅰ 天文学の転機とその意味
Ⅱ 数学的自然科学の出生
Ⅲ ガリレイ革命
10 ニュ―トンと天体力学
「天体力学をはじめて首尾一貫した理論体系として語ることに成功したのは17世紀のアイザック・ニュートンであった。ところで現在「ニュートン力学」とは言えば古典力学の代名詞と理解されている。しかし現実には、現在の力学の教科書に書かれている「ニュートン力学」とニュートン自身がその箸『自然哲学の数学的諸原理』(以下『プリンキピア』)に記したもの―「ニュートンの力学」―とは、相当に異なっている。」(本書、pp.155-156)
主要な項目は次のようである。
1 ニュートンにおける運動の法則」
2 中心力の順問題
3 万有引力の導出
4 ニュートンの限界
11 物理学の誕生
これは文句なしに面白い。読み応え十分である。著者の母校大手前高校における講演を基調にして大幅に書き換えたものである。私自身、大変に勉強になった。それというのも、確固とした多数の物理学史研究に裏付けられているからである。
主要な項目は下記の通りである。
第1限 古代の自然学と宇宙論
1 はじめに
2 アリストテレス自然学
3 アリストテレス宇宙論
4 プトレマイオス天文学
5 西ヨーロッパ中世
6 宇宙論・天文学・占星術
第2限 自然像の転機にむけて
7 懐疑論と批判のはじまり
8 コペルニクスの理論
9 地動説のもたらした問題
10 16世紀文化革命
11 二元的世界の動揺
12 ヨハネス・ケプラー
13 ケプラーの法則と力の概念
第3限 近代力学の歩み
14 魔術的自然観
15 ガリレオ・ガリレイ
16 重力を認めない機械論
17 ロバート・フック
18 アイザック・ニュートン
あとがき
Ⅲ 山本義隆『物理学の発展』
本書は12本の論考から構成されている。
1 Eulerの力学
著者(山本)はいかなる大学(アカデミー)関係の機関にも所属せず、専門家向けの論文など書くことはない。しかしこの論考(レジュメだが)だけは唯一例外で、京都大学数理解析研究所で開催された共同研究集会で報告したものである。
「18世紀のスイスの数学者レオンハル・オイラーの力学理論を、原典に即して辿ったものです。オイラーは、質量だけあり大きさの無視できる「質点」という概念を導入し、その質点に対する運動方程式を微分方程式として表し、それをすべての有形物体の力学のとして置き、その上に質点系の力学、剛体力学、流体力学を構成したことで知られています。要するにオイラーは、ニュートンが『プリンキピア』に書いたという意味の「ニュートンの力学」を、現在知られている「ニュートン力学」に書き改め完成させたのです。」(本書、p.459)
そして次のように結論する。
「Newtonが「物体の運動の法則」として措いたものを、質点に対する「運動方程式」として3次元デカルト座標成分をもちいた2階の微分方程式に表したのは、Eulerである。こうしてNewtonにおいては「極限の幾何学」としてあった力学が解析学にもとづく力学に変貌をとげ、観測される物体の運動からその物体に働く力を求める「順問題」から、与えられた力のもとで物体の運動を求める。つまり微分方程式を解く「逆問題」への力学の重心は転換された。
のみならず、Eulerは、その「質点の運動方程式」を質点の集合として諸種の物体の力学に対する「第一原理」―「その上に運動の全理論が樹立されるべき公理(『発見』15)―にとり、剛体力学と弾性体力学、流体力学の一般的理論の形成を目指した。とりわけ剛体力学と流体力学でEulerが導いた基礎方程式は、250年後の現代にいたるも有効に使用されている。とりわけ流体力学について言うならば、それまで流体の個々も問題の解決に挑んだ者はいたが、一般的な意味での「流体力学」を作ったのはEulerである。
こうして、1687年における『プリンキピア』出版以来半世紀あまり、個別の問題ごとに個別の原理を採用し個別の方法で扱われていた力学の諸問題が、Eulerの働きにより、統一的で体系的な力学のなかに位置づけられることになり、かくしてその後、力学は同時期の解析学の発展と手を携えて戦線を拡大し、内的にも整備されてゆくことになる。Eulerはまた、変分原理による力学の端緒を与えることで、Lagrange以降の解析力学への飛躍の懸橋を作った。」(本書、pp.050-051)
主要な項目は次のようである。
1 Newtonの力学(Newtonの『プリンキピア』初版1687、第3版1726)
2 『プリンキピア』以降の半世紀
3 Euler のプログラム
1 力学の解析化
2 力学の体系化・統一化
4 3次元デカルト座標での運動方程式の導入
5 Eulerによる汎通的な力学原理の提唱
1 『力学』の問題意識との継承
2 3次元直交座標で表した質点の運動法定式を、力学全体を包摂する第一原理として提唱
6 Eulerの運動法定式とNewtonの「法則」
1 Newtonの「法則Ⅰ」と「法則Ⅱ」との関係
2 「力」概念の混乱と整理と「慣性」概念の洗練
3 運動の相対性
4 非慣性系における「慣性力」の導入
7 『発見』の直接的成果:剛体の回転のEuler方程式
1 『発見』以降
2 『発見』における剛体要素の運動方程式の導出
3 『発見』における剛体の回転の運動方程式の導出
4 『発見』以後「Euler角」と「(剛体の回転についての)Euler方程式」の導出
8 流体力学の形成
1 第一の特徴 一般化
2 第二の特徴 解析化
3 座標系の導入と問題の設定
4 連続方程式の導出
5 流体要素の加速度の導出
6 運動方程式(Euler方程式)の導出
7 流体のつりあいの条件
8 (16)式の積分可能性について
9 Bernoulli の定理
10 総括
9 変分原理と最小作用の原理
1 つりあいとポテンシャルの極小
2 モーペルチュイ(Maupertuis)の原理
3 Eulerの功績(その1)変分法におけるEuler方程式の提唱
4 Eulerの功績(その2)最小作用の原理の提唱
10 結論
2 『解析力学』出版200年によせて
「Lagrangeの『解析力学』の初版は1788年、Newtonの『プリンキピア』初版出版の101年後、フランス革命勃発の1年前にあたる。・・・力学理論に対する本書の直接的な貢献は、一般化座標の導入と、それによる力学原理(運動方程式)のいわゆるLagrange方程式の定式化である」(本書、p. 53)
「このような組織的・体系的教育のためには、力学すなわち機械学は、それぞれの問題ごとにそれに即した技巧や工夫、つまり「天才のひらめき」を要する非体系的な問題集成や、適用範囲の限られた特殊理論では役に立たない。求められていたのは、汎用性を有し、体系化されているのみならず、機械的・操作的に扱え、それゆえ一定の訓練を積んでさえいれば誰がやっても巧拙なく解を求めうるマニュアル化されたアルゴリズムを持ち、さらに、科学の進歩に伴って適用範囲を漸次拡大しうる一般性を有している理論でなければならない。
それを初めて提供したのが『解析力学』であった。「19世紀の最初の三分の一のあいだヨーロッパ全体はパリから放射される科学の光によって照らされていた」(Merz)と言われているが、Lagrangeの遺産は今もって目減りがない」(本書、p.61)
3 カントと太陽系の崩壊
「私の乏しい知識の範囲ではあるが、哲学書でも科学史書でもカントとラプラスのあいだの決定的な相違がこれまでほとんど見落とされ無視されてきたようだ。それは、ラプラスが太陽系の力学的安定性―いわゆる「ラプラスの定理」―を少なくとも摂動の一次までの範囲で証明したのに反して、カントはひとたび形成された太陽系もやがて崩壊し消滅すると主張したことにある。いわく「完成されたどの宇宙も徐々に没落に向かう、・・・、有限なもの、始原を有するものはすべて、その本性が限られたものであることの微を宿している。それは必滅の定めにあり、やがて終末を迎えるにちがいない」。カントが描き出したその終末は、すべての惑星と彗星が、太陽に落下した後、太陽は巨大な灼熱の球に膨張し、ついにはすべての物質を元素に分解し原初の混沌に吹き飛ばすという壮大で苛烈なドラマであって、じつは現代物理学が予測するシナリオを一部、先取りしているのである」(本書、p.62-63)
4 幾何光学と変分法
「変分法は、もともとは最速降下線の問題、つまり、重力の作用を受けている質点が所与の2点間を最短時間で降下する曲線を求めよというパズルのような問題から始まったが、一方では純然たる数学的立場から拡充整備されるとともに、他方で物理学においては、幾何光学や古典力学の枠組みを与えたばかりか、現代の場の量子論の必須の道具となるまでに至っている。ここでは、力学に比べて語られることの圧倒的に少ない幾何光学の変分法による定式化を通して、物理学と数学の関わりを見ることにしよう」(本書、pp.068-069)
主要な項目は次のようである。
1 変分法とフェルマの原理
2 ワイヤシュトラスーエルドマンの条件
3 測地場とハミルトンーヤコービ方程式
4 ホイヘンスの原理
5 力学と熱学
「これまで古典物理学(とりわけ熱力学)の諸問題の検討に際しては、多くの場合、微視的なレベルに引き戻して論じる還元主義的が支配的であった。それは古典力学の大方の創始者たちが原子論者であったことにもよるだろうが、なによりも20世紀における微視的物理学――量子物理学―の目覚まし成功が決定的である。しかし18~19世紀にける熱学と熱力学の形成は、一方では、全地球的規模での物質循環・熱循環の発見に促され、他方では、火力発電の発展に伴うその効率向上を主要な問題意識として進められてきた。このことを鑑みるならば、そしてまた、それらの問題の現在にも通常する意義を認めるならば、古典物理学を巨視的物理学の枠内で見直すことも、優れて現代的意義を持つことではないだろうか」(本書、pp.85-86)
主要な項目は次のようである。
1 はじめに―巨視的力学で説明のつかないこと
2 力学の起原としての機械論の一面性
3 ニュートンの反機械論
4 二元的物質観と熱学の起原
5 カルノーの定理と熱現象の非可逆性
6 温度と熱――熱エネルーの特殊性
7 エントロピ―と自然の非可逆性
6 スコットランドとイングランド
「ちなみに電磁気学の基礎を作り上げ、その方程式に名を残すマクスウェルもまた、前記のようにスコットランドの出である。なんのことない。18・19世紀のイギリスで物理学研究の先端を担ったのはオクスブリジの「純イギリス人」エリートではなく、その多くがスコティッシュであった。それにしてもトムソンやマクスウエルのケンブリッジにおける冷遇には、「文明の国」大英帝国を訪れた長岡半太郎もさぞかし驚いたであろう。最先端の近代科学もナショナリズムという文明の病には勝てなかったのである。」(本書、p.128)
7 ケプラー問題の初等的解析と離心ベクトル保存について
「以上、ケプラー問題の内部にこれだけのことが秘められていたことは、まことに驚くべきことであろう。17世紀はじめに対称な円軌道を放棄したケプラーを非難した友人ファブリチウスに対するケプラーの次の反論「真の単純性は、天文学理論の基礎にある諸原理に関して求められるべきであります。私の説の場合、もしもより小数の普遍的諸原理からかくも多様な諸現象が帰結するのであるとしたら、それでも君は、かかる結果の多用性を理由に原理の単純性を否定するのでしょうか」は、予言的であり、今なお光彩を放っているのである」(本書、p.166)
主要な項目は次のようである。
Ⅰ 問題の設定と歴史的背景
Ⅱ 保存性と対称性
Ⅲ ケプラー問題とホドグラフ
Ⅳ 惑星軌道の初等的な求め方
Ⅴ ケプラー問題のいまひとつの解法
Ⅵ 離心ベクトルと対称性
8 アブラハム・パイスとニールス・ボーア
「アブラハム・パイスの名は、アインシュタイン伝として名高い『神は老獪にして…』(産業図開)の著者として、一般には知られている。同書の読者であれば、それが伝記作家やジャーナリストの手になる凡庸の伝記ではないことをご存知だろう。実際、同書には、アインシュタインの量子論への貢献や一般相対論の形成が正確かつ詳細に記されているばかりか、アインシュタイン以後の宇宙論や重力理論の発展にも叙述が及んでいる。並の歴史家や電気作家の真似のできないところである」(本書、p.169)
9 量子論から量子力学へ―量子力学入門
「19世紀の末期にほぼできあがっていた物理学、とくに力学は、以後、古典物理学、とくに古典力学、ひっくるめて簡単に古典論と呼ばれる。古典物理学は巨視的世界、つまり原子や分子が10の何乗個も集まってできている世界、長さがセンチメートルやメートル単位で、質量がグラムやキログラム単位で測定される世界では、きわめて有効であるが、しかし世紀の変わり目に、原子や分子が1個や数個からなる微視的世界では古典論では説明できない現象が見出されていたのである。最終的には微視的世界の物理学の原理が見出されたのが1925-26年であり、その物理学と力学を量子物理学、量子力学という。」(本書、pp.174-175)
主要な項目は次のようである。
1 はじめに
2 ケプラー運動の古典論
3 水素原子の量子化
4 量子力学への手がかり
5 古典力学の変分原理
6 波動方程式を導く
7 波動関数の意味について
8 量子力学における状態と物理量
9 不確定原理について
10 角運動量の背理について
11 おわりに―経路積分の概略
10 対応原理と相補性原理
「20年後の1949年にBohrは、「相補性」の提唱にとって「原子的対象の振る舞いと、その現象が発生する条件を定めるのに測定装置との相互作用の明確な分離が不可能なこと」にもかかわらず「現象が古典力学で説明のつく範囲をどれほど超越しても、すべての証拠は古典論の用語で表さなければならない」という認識が決定的であるとあらためて確認している。この議論の延長線上に、「現象という言葉の使用を、もっぱら実験全体の説明を含む特定された状況のもとで得られる観測のみを指すものに限定する」という、後年にBohrが到達した立場が確認されてゆく。それは、量子力学の完全性をめぐるEinstein との論争の中心テーマであった。対応原理がコペンハーゲン学派による量子力学形成の指導原理となったとすれば、相補性原理は量子力学のコペンハーゲン解釈の基礎となったと言える。」(本書、pp.241-242)。
主要な項目は次のようである。
1 発端
2 対応原理
3 量子力学へ
4 相補性原理
11 55年目の量子力学演習
「大学に入学し、二年の秋に理学部の物理学科に進学が決まり、その後、大学院の修士課程の頃まで、それなりに幾つも講義を聴いている。そのはずだけれども、聴くのが下手だったのか、黒板に数式を書かれてもそれを目で追うだけでは頭には入らなかった。・・・・。そんな次第で、いま顧みて思うに、講義で身についた物理というのは少なかったようだ。担当は、当時、素粒子研の助手であった江沢洋さんと、もうひとり物性理論の助手の方であったが、今思い返しても、この演習、とりわけ江沢さんの指導が、私の物理学の学習には大きかったように思われる。それは単に知識の問題だけでなく、物理学に向かう姿勢も含めてそうであった」(本書、pp.244-245)
主要な項目は次のようである。
1 回想の量子力学演習
2 思いついたことはやってみるという教訓
3 ディラック論文について
4 量子力学を教えること・学びこと
5 「君にとって量子力学とは」
6 シュレディンガー方程式にいたる
12 相対性理論入門講座
本論考は著者の初めての相対性理論の講義である。その講義は1980年頃、勤務先の駿台予備学校で行った教養講座のものだ。ああ、これが山本の相対性理論か、と思いつつ、そのきめ細やかな論述の展開に圧倒され唸ってしまった。また、長きにわたる物理教育者のきわめて細やかな教育的配慮が見てとれる。
主要な項目は下記のようである。
第1章 ニュートン力学の相対性
1 コペルニクスの遅動説
2 ガリレイ変換
3 ニュートン力学へ
4 相対性原理・共変性原理
5 音のドップラー効果について
第2章 電気磁気学の問題
1 光の伝播速度の測定
2 地球上で測った光速
3 マクスウェルの電磁場理論
4 エーテルと光の伝播速度
5 マイケルソン達の実験
6 さしあたっての解決
7 ローレンツ収縮の一つの帰結
8 ローレンツ変換
第3章 特殊相対性理論
1 アインシュタインについて
2 光速不変の原理
3 ローレンツの変換再論
4 長さの縮みと時計の遅れ
5 速度の合成法則
6 同時刻、未来、過去
第4章 相対論力学
1 4次元ベクトル
2 波数・振動数ベクトル
3 運動量とエネルギーの決定
4 エネルギー・運動量ベクトル
5 光子量子の立場から
6 荷電粒子に働く電磁力
第5章 公式E = mc2 をめぐって
1 質量とエネルギーの関係
2 結合エネルギー
3 核分裂反応について
(本書全体の)あとがき 物理学について、私がこれまで書いてきたもの
Ⅳ おわりに
後者の『物理学の発展』の最後に、「あとがきー物理学について、私がこれまで書いてきたもの」が付されていることに注目されたい。そこには「今後、このようなことを書く機会もないと思われるので、私がこれまで物理学について書いてきたものについて、簡単に触れておきます」(本書、p.465)とあります。それはいわば、著者が「80余年の人生の終活は、60余年の活動の総括でなければならい」(本書、p.475)と述べているところである。
その概要を簡単に述べておく。物理学の研究者が東大闘争の結果、物理学の研究者であることを辞退(拒否)し、ある会社勤務を経て予備校の講師として物理教育に関わる仕事をしながら、かずかずの重厚な物理学と科学史の著書を上梓し刊行してきたことなどが、たんたんと述べられている。そこに言及されているすべての書群を読み込み学んできた私は、感動の念を禁じ得えないのであり、長年のご指導とご鞭撻に深謝するのみなのである。
