自分たちでオリジナルのアーカイブをつくる
▶『映像アーカイブ・スタディーズ』の読書会と市民科学研究室のアーカイブ◀
瀬野豪志(市民研「アーカイブ研究会」世話人)
PDFはこちらから
『映像アーカイブ・スタディーズ』の読書会
今夏からアーカイブ研究会の読書会で扱うのは、この本です。
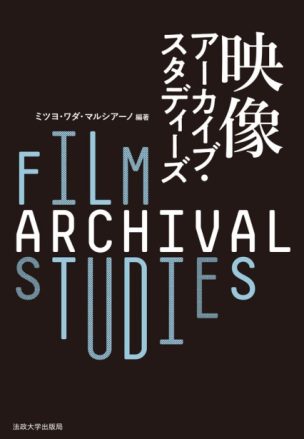
ミツヨ・ワダ・マルシアーノ編著『映像アーカイブ・スタディーズ』法政大学出版、2025年
まず、編著者による序章で、現在の日本における「映像アーカイブ」の問題が明示されています。各章にはいくつかの論文があり、基本的な問題から、国内、国外、メディア、周辺的なものへと広がっていくように全体の構成が整理されており、この問題のテキストとしてとても読みやすい論文集です。(「第I部 映像アーカイブの現状」、「第II部 国内を見つめる」、「第III部 国外を眺める」、「第IV部 他メディアの場合」、「第V部 周辺化されたシネマ」)
そして、編著者の「終章 研究から実践へ」では、地元の京都での「映像アーカイブ」の可能性について書かれており、様々な機関との連携を構想しながら、この本は閉じられています。つまり、この問題は本を閉じてからが肝心であるような、そんな印象もあります。
この読書会は、「映像アーカイブ」についての問題や議論を全体的に理解していくと同時に、市民科学研究室において企図している「科学映像」のアーカイブをつくるにはどうしたらいいか、ということを考えながらやっていきたいと考えています。つまり、市民科学研究室での実践的な問題は、「科学映像」とはなんぞや、それは、どのようにつくられ、いまどのようにあるのか、アーカイブとなるとどのようなことが見えてくるか、どのようにアーカイブにしていくのか、というようなことにあります。まずは、映像アーカイブについての基本的なことを学びながら、「科学映像」について調べていきます。
わたしが「科学映像」アーカイブについての調査の報告をするときは、この通信や下記のサイトで、「自分たちでオリジナルのアーカイブをつくる」という観点から、市民科学研究室でのアーカイブの活動を公開しながら、この読書会で議論された内容についての紹介もしていきたいと思います。
◆科学映像アーカイブ・スタディーズ(読書会、科学映像アーカイブについての調査による情報)
市民科学研究室がつくるアーカイブについてのアーカイブズ
市民科学研究室の動画サイト「くらしとかがくのアーカイブ」は、コロナ禍の中にあった2021年から始めています。
市民科学研究室の理事会や運営会議でわたしが提案していたときの文書(アーカイブズ)をもとにして、この動画アーカイブがつくられてきた経緯を辿ってみましょう。
2018年8月29日の理事会において、わたしは「市民研アーカイブ 会員向けの動画、音声のアーカイブ」と題して、次の3つのタイプの動画を制作する提案をしています。
- 講座やイベント
- ニュース(週一回、10 分以内)
- 訪問インタビュー
2018年頃、コロナ禍の前は、講座やイベントの会場で収録された動画は残っていますが、現在のようにオンラインの講座や会議は行われていませんでした。動画だけで見てもらう動画づくりとして「インタビュー」の動画を提案していましたが、「訪問インタビュー」となっているのは、Zoomのような遠隔的な動画収録の手段がなく、事務所で動画だけを収録するようなこともなかったからでしょう。
市民科学研究室で動画をつくるなら、どのようなものをつくったらいいだろうか。「インタビュー」はすでに市民科学研究室では実績があるので、すぐにできるのではないかと考えたわけです。動画版になれば、「インタビューとともに、キャンパス、研究室の様子、実験の実演なども」見せられると書いてあります。
東京都の小池知事が「感染爆発の重大局面 今週末の外出自粛を」という記者会見をした2020年3月25日に(確か事務所で理事会がありました)、「インタビュー企画案」という題で、わたしはこのようなレジュメを作成しています。
「研究の現場から」シリーズ
・大学、企業、組織を問わず
・子ども、学生などに向けて(親、学校・塾に加えて、第三の情報源として)
・パーソナルなことと社会・文化の間に「科学」を位置付ける倫理的な対話
(市民科学の場でないとできない対話として考える)
流れ
はじめに、「研究」の現場をちらりと撮影させてもらう
まくらとして、その研究(分野)に関わる政治的問題、よく知られている出来事、事件
その人の研究歴、とくに子どもの頃、学生の頃、現在の研究につながっているか
その人の仕事論、お金の話、あるいはお金ではないという話
その人の科学論、その研究(分野)はいかにして「科学」になっているのか
その人の社会論、どういう意味があるの?なんでそこまでするの?と子どもに聞かれたら
研究をどのように維持していくのか、拡張していくのか
次世代にどのように継承してもらいたいか、など
引出したいこと
パーソナルなことを話した上で、専門的な研究との揺れ、社会・文化への態度を引き出す
「本当はこうしたいんだけどなあ」「どう言われるかわかりませんが」など
落としどころ
どのような研究ができるといいのか(次世代?の視聴者にとってもヒントになる)
その研究者への問い合わせやメッセージがある方は、市民科学研究室へ
フル動画、他の動画は、市民科学アーカイブへ
コロナ禍になると「訪問」のインタビューは難しくなりました。しかし、この案をもとにして、まずは、上田さんの「人生としての科学と社会」という動画を収録してみて、市民科学研究室の会員でやってみようということになり、杉野さんの「ブックトーク」案も取り入れた「語っていいとも」の動画につながっています。2020年11月からの市民科学入門講座も、会員の皆さんのことがよくわかる動画のアーカイブになっています。
2021年3月26日の理事会でわたしが提案した内容の文書には、「事務所を活用した、デジタルアーカイブでの配信、発信、連携を進める」「市民科学研究室におけるデジタルアーカイブの理念、目的」「自らの問い、プロジェクト、研究会の過程を共有する」とあり、次のような動画の企画が書かれています。
- それぞれの動画を月一本以上制作する
・表示について 「加工食品の表示 ○○ってなんだ?」(YouTube、15 分以内)
・書評や時事問題 「自分で調べる研究室 ○○について」(YouTube、15 分以内)
市民研にある蔵書や資料を手に取りながら
どのような資料があるか、さらにどのように調べようとするか
「自由研究」についてのトーク 学校の先生に聞く、ヒントや実演、オトナの自由研究、自由研究の思い出など
「科学番組」についてのトーク さらに調べるには、考えるべきことなど
・インタビュー 「人生としての科学と社会」(会員向け、60 分程)
市民研の関係者や会員から(市民科学への)分野や経歴の違いに着目して制作する
(本来は子ども向け、YouTube で公開できる場合はダイジェスト版)
- 動画制作をもとにしてアーカイブにする(2021 年内)
・「科学と社会を考えるアーカイブ」というテーマを掲げて、動画や音声に関連するデジタルコンテンツをまとめていく
この頃、「みらい会議」と言っていた運営の企画会議で、新しい会員制と、非会員も含めた準会員的なファン層(YouTubeを始める)、会員同士のつながり(動画制作とそのアーカイブ)などの市民研の動画制作の目的について、わたしが話していたことの記録が残っています。今見ると、それなりに当初からの延長線上にあるような動画もあれば、忘れかけていたことや、まだまだできていないようなこともあります。先日のノンアルコール試飲会のような、研究会から企画して作られる動画や土曜イベントなど、あらためて面白そうな発想があるのを見つけました。
「訪問」の動画は、コロナ禍が明けてから、徐々に増えてきています。そのきっかけとなったのは、子どもシェフの農業体験や、アイカム社と市民科学研究室による科学映画シンポジウムの動画です。まだマスクをしていたのが映像に残っています。

【参考】連続講座「めざせ、子どもシェフ! 食と農のとびっきり体験」全記録
◆科学映画シンポジウム「いのちの科学映像が 切り拓くもの―アイカムの50年の足跡から考える」(2022年11月23日)全記録
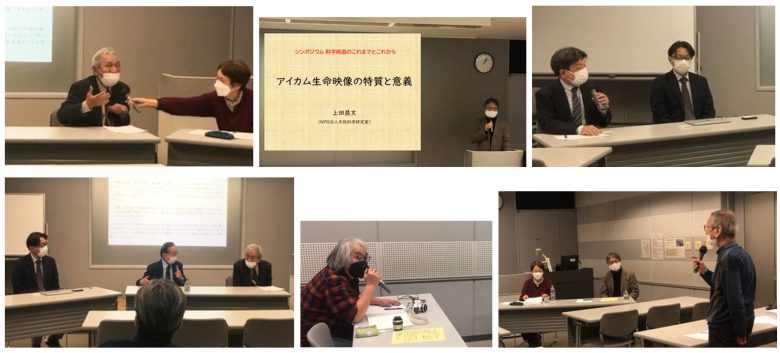
その後は、土曜ランチで薮玲子さんに紹介していただいた岩城正夫先生や、壹岐さんと橋本さんによる世界農業遺産スタディツアーでは、当初想定していた範囲を越えた訪問インタビューになっています。
【参考】スタディツアープロジェクト
映像のアーカイブも、映像についての記録となりうる資料群(アーカイブズ)を辿ることによって、残されている映像そのものと、どうしてそのようにその場でその時に収録されたのか、ということがわかります。これまでの動画制作の経緯も改めて認識しました。
「アーカイブをつくる」経緯がどのようであるかという観点からも、映像やその資料群(アーカイブズ)が見られていくようになると、さらにいろんなことがわかるのではないかと思います。これは「科学映像」にも適用できることではないかと、わたしは考えています。
昨年の図書館をめぐる信州ツアーで感銘を受けたことのひとつは、「信州風樹文庫」で案内された資料室にあったリュックサックでした。戦後間もない、本がなかった頃に、岩波茂雄の故郷の若者たちが岩波書店に本の寄付を求めて、リュックサックで東京から本を持ち帰って以来、今でも岩波書店からの出版物が寄贈され続けているという、その成り立ちが伝わる資料とその地元の人々によってオリジナルの図書館が存続していることに感銘を受けました。
市民科学研究室の蔵書をもとにした「自分で調べる図書館」
市民科学研究室には、約5000冊の書籍、小冊子、雑誌などの蔵書があります。私設の「自分で調べる図書館」として、その蔵書を様々な形で活用できるようにするために、目録のデータベースをつくっています。
◆自分で調べる図書館 「蔵書検索」「蔵書の評価・レビュー」「最近追加した資料」
◆自分で調べる図書館サイト(利用案内、イベント、「調べる」活動・レファレンスのアーカイブ)
目録のデータベースづくりは、常に更新し続けるアーカイブ的な活動です。「検索」「評価・レビュー」「更新情報」は、まず第一歩となる機能ですが、データベースをつくることで可能となる、蔵書に関する最新情報の公開サービスです。
名前の通り、「調べる」ために活用できる図書館となることを目指して、研究活動、調査プロジェクト、イベントなどによって収集された資料、つくられた資料、活用された資料、記録を保存し、蓄積し、整理し、新しい「調べる」活動につながるように、公開していくことを目論んでいます。
これから整理する資料、新しく収蔵された資料も入力していきます。今夏は、報告書などの小冊子や、アイカム社の映画や放送番組などの市販されているDVDの情報も入力していく予定です。
アーカイブ研究会の読書会、自分で調べる図書館(図書館プロジェクト)の参加者を募集しています。いつでもお気軽に市民科学研究室までお問い合わせください。■
市民科学研究室の活動は皆様からのご支援で成り立っています。『市民研通信』の記事論文の執筆や発行も同様です。もしこの記事や論文を興味深いと感じていただけるのであれば、ぜひ以下のサイトからワンコイン( 10 0円)でのカンパをお願いします。小さな力が集まって世の中を変えていく確かな力となる―そんな営みの一歩だと思っていただければありがたいです。ワンコインカンパ ←ここをクリック(市民研の支払いサイトに繋がります) |
