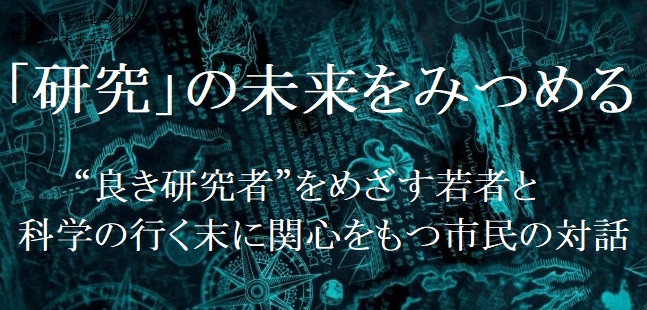
2025年4月から月に1回のペースで、原則として「土曜広場」の枠を使って、次の「自由討論シリーズ」を実施します。多くの方々のご参加をお待ちしています。
自由討論シリーズ
「研究」の未来をみつめる
―“良き研究者”をめざす若者と科学の行く末に関心をもつ市民の対話
現在、大学院(あるいは学部)に在籍して、未来を切り開く研究に着手している人たちに登壇いただき、どんな内容の研究に取り組んでいるのか、それは世の中に何をもたらしそうなのか、その研究を志すようになったわけは、そしてどんな研究者を目指したいか……を語ってもらいます。それを受けて参加者(20名まで)と自由な雰囲気で対話します。
若い方が研究者として身を立てていく、その初期の段階から、市民とのよい形での対話の場を持つことが、科学をより良いものにしていくことにつながる、と私たちは考えています。研究の未来に興味を持つ方ならどなたでもご参加ください。
第8回
時空間スケールにおける温熱環境評価の深化と展開
登壇者:廣木亮哉さん (東京科学大学融合理工学系博士後期課程3年、専門領域: 生気象学、都市気象)
<内容紹介>
日時:2026年2月14日(土)10:00-11:30
参加方法:オンラインでの実施(市民研事務所にいらしての参加も併用)
参加費:無料
🔶お申し込みは下記のフォームから🔶
進め方:
1)登壇者による研究内容の紹介とそれにまつわる自分の思い(30分)
2)登壇者と市民研代表の上田との対話(15分)
3)参加者との意見交換(30分)
4)参加者全員が感想をチャットに記す(10分)
共催:NPO法人市民科学研究室+リベラルアーツ協会
協力: LabTree
初回無料視聴のサービスも設けています。視聴を希望される方はこちらをご覧のうえ、ご連絡ください。
【これまでに実施した講座】
▶動画はすべて「くらしとかがくのアーカイブ」に収めています。
第7回 太陽光をナノの世界で集め活かす分子システムの構築
日時:2025年12月20日(土)10:00-11:30
登壇者:松本昂大さん (九州大学工学府応用化学専攻 博士2年)
<内容紹介>
私たちは日常的に太陽光を受けていますが、自然界では植物が光を効率的に集め、エネルギーに変換する巧妙な仕組みを持っています。本講演では、そのような光の捕集やエネルギー変換の原理を参考に、ナノ空間で光を操りより高いエネルギーを生み出す研究を紹介します。具体的には、金属ナノ粒子と光の相互作用により局所的に光を増幅するプラズモニックナノ界面を作り、その場で分子の吸収やフォトンアップコンバージョン現象を増強する取り組みです。こうしたナノ空間の設計と制御により、光エネルギーを効率的に利用できる分子システムの構築を目指しています。講演では、光と分子の関係、ナノ界面の作製方法、そして研究の面白さや応用の可能性について、わかりやすくお伝えします。
第6回 生き物の形を記述する技術としての数学を作りたい
2025年11月29日(土)10:00-11:30
登壇者:島田 草太朗さん(東京都立大学 理学研究科)
<内容紹介>
数理生物学や理論物理学など、数式を使う分野はたくさんあります
私の今の分野は、生き物の形に関する応用数学です。それが数理生
<「研究者トランプ」によるプロフィール>
生き物をみる数学という名の眼鏡を作る
アルキメデス、ガリレオ、ライプニッツ、オイラー、ガウス、ポアンカレ、などなどがもし、物理よりも生き物が圧倒的に好きだったなら、数学はどのようなものになっていただろう。きっとそこには今人類が知っている数学の世界とは違ったパラレルワールドがあったはず。そこでは、生き物は、数学は、世界は、どう見えたのであろう。物理学者より生物学者の方が数学が得意だったかも。その世界を夢見て、数学を作っていこう。
第5回 歯科情報による健康支援と防災時の身元認証システム
日時:2025年11月1日(土)14:00-15:30
登壇者:吉濵健一郎(よしはま・けんいちろう)さん (一橋大学 博士(社会学)/同大学 特別研究員)
<内容紹介>
東日本大震災をきっかけに、「破壊」を経験した社会に関心を持ち、以来このテーマを軸に研究を続けています。大学院では、約30年にわたる内戦を経験したスリランカ社会を対象に、紛争の要因と変遷、そして戦後の和解プロセスについて探究しました。
現在は、災害や紛争などによって命を失った人々の身元確認という課題を、地球規模の社会的課題(グローバル・イシュー)として位置づけ、研究を行っています。特に、歯科情報を用いた身元確認の可能性に注目し、その社会的意義や制度設計を社会科学の視点から検討しています。同時に、研究と並行して実際に日本国内での仕組みづくりにも取り組んでいます。
歯科情報は、災害や事故といった「有事」における身元確認だけでなく、日常の健康管理や地域医療の連携といった「平時」にも活用できる可能性を秘めています。今回の講演では、こうした「有事と平時をつなぐ歯科情報のあり方」について、みなさんとともに考え、よりよい社会の実現にむけた道筋を探っていきたいと思います。
第4回「総合知を形成する社会貢献的なSNSの構築」
日時:2025年10月25日(土)14:00-15:30
登壇者:船岡 佳生(ふなおか よしき)さん(日本リベラルアーツ協会 代表、Poetry Factory 主宰)
<プロフィール>
理系出身ながら、文学・芸術・哲学・教育を架橋するべく、詩の総合事業「Poetry Factory」を立ち上げ、ことばと想像力を軸にした表現・対話の場を企画・運営している。また、研究室の議論を増やすプロジェクト「LabTree」を通じ、議論・思考・創造を支えるアプリ開発も行なっている。文学とテクノロジー、地域と教育のあいだをつなぐ活動を広く展開中。
<内容紹介>
社会や個人にとって良い働きをするSNSの構築を目指している。結果的に総合知の形成と、社会教育、個人の内面のアーカイブ構築に帰結することが開発の狙いである。そのために必要な理論や論点を整理したい。背景は、以下の2点である。1にインターネットの普及により、Wikipediaなどの誰でも編集可能な知の辞典は生まれたが、市民レベルで関与しているとは言い難い。広く、オープンなWEBによる総合知の形成は、各分野別や話題毎に行われており、強い目的志向を持ったプラットフォームは現状見当たらない。2に他方で、インターネットやSNSによる情報の正しさや、個人の意見表出が誹謗中傷レベルまで進むことが社会問題化している。これら2点を同時に解決するSNSの構築を目指している。構築中のSNSは以下にて確認可能である。(ただし10月15日現在、キュリティ上の問題があり、自己責任で閲覧や登録を行なってください。https://app.liberalarts7.co.jp/)コミュニケーションエラーの課題と刹那的でない知の蓄積、発展機能を持たせられることを目指しているが、諸課題も山積している。そのため人間と情報、メディアといった知からの演繹的なアプローチもより必要だと考えている。アーカイブ研究会で経験したことや、議論したことが確かベースとなってこの挑戦をしている今、市民研の皆様との忌憚の無い議論をとても楽しみにしている。
第3回「美は世界を救う」を心理学で実証したい
2025年8月16日(土)14:30-16:00
登壇者:櫃割仁平(ひつわりじんぺい)さん(京都大学で博士号 (教育学) を取得、現在はドイツのハンブルクにあるヘルムートシュミッド大学でポスドク研究員)
<内容紹介>
日本的な芸術題材(俳句、雅楽、書道、いけばななど)を通して、人がどのように美しいと感じるか、そしてその効果などを研究しています。これまで芸術認知の研究は西洋が中心的なフィールドでしたが、日本の美的感性には独特なもの(わびさび、間、曖昧さなど)もあると考えており、それらを研究したいと考えています。最近は、ドイツで研究滞在を行っており、日本人とドイツ人の美的感性の比較を行っております。「美しい」とはどういう感情なのか、そしてそれは人や社会にどういう影響をもたらすのか一緒に考えたいと思っています。
第2回 「日本の言語景観における漢字字体顕在化モデルの構築:社会・文化、技術、権力の可視化」
2025年7月15日(火)20:00-21:30
登壇者:石井諒太さん(東京科学大学博士1年)
<内容紹介>
私の研究の目的は、日本の都市空間で交錯する様々な漢字字体の選択—例えば「学」と「學」—を対象とし、都市空間に現れるあらゆる言語標示(言語景観という)を媒介に、顕在化する文字の背後にある社会・文化・科学技術・権力の構造を明らかにすることである。これまでも日本語の新・旧字体に関する研究が存在し、個人が持つなじみや好みといった表層的な心理や、それらの背景にある単純接触効果などを扱ってきた。日本以外にも歴史的に漢字を用いてきた漢字文化圏には、中国大陸・シンガポール、台湾・香港、韓国、ベトナムなどが含まれ、国・地域ごとに異なる標準字体を用いてきた。そこで私の研究では、日本において混在する中国語繁体字・簡体字など、多言語社会化した日本で生じる字体選択行為を対象にする。例えば、横浜中華街をはじめとする複数のチャイナタウン-中国語使用者が日本語使用者を迎える-において、中国語標示の収集、文字体系や標示物に応じた分類、そして標示の書記者・所有者に対する調査を実施し、字体選択の社会・文化的動機や技術的制約そして言語を統制するオーソリティの影響を多面的に分析している。既存の枠組みを超える新たな漢字字体選択モデルの構築を通じて、多言語社会における包摂的な書記環境の実現に資することを目指す。
第1回 「宇宙データ可聴化について」
2025年4月26日(土)13:00-14:30
登壇者:藤本未来さん(東京科学大学博士2年)
<内容紹介>
データを音で表現する可聴化は、近年宇宙分野で著しく発展しています。宇宙データをどのように音で表現することで、どんな目的が達成されるのかを紹介します。
