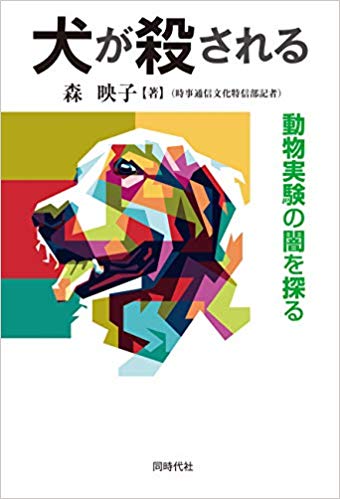
書評
科学の裏側に隠された実験動物たちの今を知る―
『犬が殺される―動物実験の闇を探る』(森映子著 同時代社2019)
東さちこ(「PEACE 命の搾取ではなく尊厳を」代表)
PDFはこちら
「科学」の名のもと行われる動物実験。そこでは、動物にされていることだけを見れば、虐待と区別がつかないことがさまざま行われている。例えば、動物実験の約半数を占めるであろう安全性試験などの試験系では、麻酔や鎮痛などのための薬剤が使われることは(近年のごく一部の例外を除き)ありえない。
動物虐待と見分けがつかないからこそ、欧米諸国は早くから動物実験について法的な規制を取り入れてきた。EUは、施設や実施者だけでなく動物実験計画自体も国などの許可制となっているし、アメリカは動物実験施設が登録制だ。
しかし日本では、諸外国の動物保護法・福祉法にあたる「動物愛護法」で、3R(動物実験の代替、削減、苦痛の軽減)の原理原則がうたわれているものの、実験動物の保護・福祉に関する公的な仕組みをつくらなければいけないという意識は希薄である。
背後には、動物実験に関わる人々が内実を明かさず、アンタッチャブルな空気をつくってきたことがある。社会は、実験動物の置かれている状況に、気が付いていないのだ。
そこに登場した本書、『犬が殺される―動物実験の闇を探る』は、日本で初めてと言える画期的なルポルタージュだ。時事通信の記者である森映子さんが、多くの取材拒否にあいながらも、日本の動物実験の現場を取材して歩いた記録である。
冒頭、日本獣医生命科学大学で近年まで続けられていた、5日間、同じ犬を開腹・開胸手術しては閉じ、また開きを繰り返す外科実習という、強烈な話から始まる。「犬は痛がってキューンキューン鳴き叫んでいた」。だめだ、読めない!と思う人もいるかもしれないが、こういった生の声こそ、成果だけが公表されることの多い動物実験で語られてこなかったことだと、私は思う。
あれだけ加計学園問題で話題になった獣医学教育も、国際的な流れを受けてどのように変わりつつあるのか、動物の扱いという観点ではあまり語られなかったが、本書では実験動物利用から臨床教育重視への転換について、大学の今を知ることができる。
そして、東北大学医学部の動物実験施設で実践されている「看護的飼育ケア」。裏を返せば、動物実験がいかに動物の体に苦痛を与え、心身にストレスを与えるかということなのだが、新しい試みには、動物の命について何かを気付かせる希望もあることが感じられる。
また、全体を通じ、著者が実験動物の痛みに関心を寄せていることは特筆に値する。動物について、もしくは動物実験について、抽象的な議論はしばしば行われるが、動物たちが痛みや苦痛を感じるリアルな存在であることが置き去りになっていると感じることが往々にしてある。本書は、その点でも事実を追及しようとしており、また、著者が動物の痛みに敏感だからこそ、しばしば動物実験に対してとられる現状追認のような態度ではなく、動物を用いない安全性試験への代替などの話題にも話が及ぶのだろうと感じている。
一方で、動物の胚にヒトの細胞を入れ、動物と人のキメラをつくる技術(動物性集合胚)の研究など、科学の向かう方向性に疑問を感じざるを得ないテーマも本書では取り上げられている。最終的に規制緩和されてしまったが、文部科学省が、推進派を集めた委員会でいかに独善的な采配を振るってきたか、そして座長が中立の立場でなく、いかに推進を明言していたか、私自身も傍聴を重ねた中で憤りを感じており、この政策決定過程の問題点が記録として残されたことは、本当に価値があることだと思う。
そして今、動物愛護法も改正の動きが佳境に入っている。日本では、動物実験施設の届出制(もしくは登録制)すら関係者が受け入れておらず、これまで公的な査察すら、制度がない状況が続いてきた。そのことを著者は真正面から批判している。
今回も実験動物の扱いについては法改正が見送られる公算が高いのが現状だが、このように市民と同じ目線で訴える著作が登場したことに、心から感銘を受けている。日本も変わっていくことを心から願うし、変わっていかざるを得ないだろう。
本書はまさに、変化の途上にある動物実験の「今」をとらえた著作であり、今読むことももちろん価値があるが、10年後、20年後に、あの頃はどうだったのかと振り返るときにも貴重な記録となるだろう。
本書にも登場するが、酪農学園大学で学生に引き取られた元実験犬の「しょうゆ」ちゃんが、いかに一般家庭で愛されて、犬らしく暮らしているかを知れば、だれしも明るい気持ちになる。これまで動物実験の現場で殺されてきた数多くの実験犬も、本当は、同じように犬らしく生きる権利を生まれ持っていたはずなのだが、それは叶わなかった。
思えば、現在、動物の権利/福祉のための団体を立ち上げ活動をする私自身が、2000年に個人サイトをつくったのも、1匹の実験用マウスをもらって飼い始めたことがきっかけだった。小さなマウスにも、生きるための知恵があり意思がある。そして苦しむ存在なのだ。
彼らを犠牲にして成り立っている現代社会の在り方を見直すためにも、ぜひ多くの方が本書を手にとり、考えてみてほしいと願っている。
【続きは上記PDFでお読みください】

日本の動物実験における「虐待」に対して、何故、その惨忍な行為を行っている獣医や獣医学生自身から疑問や反対の声が何十年にも渡って上がってこないのか。不思議でならない。馬鹿ではないかと思うぐらいだ。このこと自体が日本の後進性を物語っていると思う。高学歴、エリートと言われる人間にさえ哲学が無い。「命の哲学」が無い。国民に哲学が無いことが原発問題、子供の虐待、差別、そして動物虐待、生体販売をするペットショップの存在等々々、他の先進国に遅れを取り、法改正等が進まない原因ではないだろうか。他の先進国の姿勢を学ぶ、真似ることもできないのだろうか。