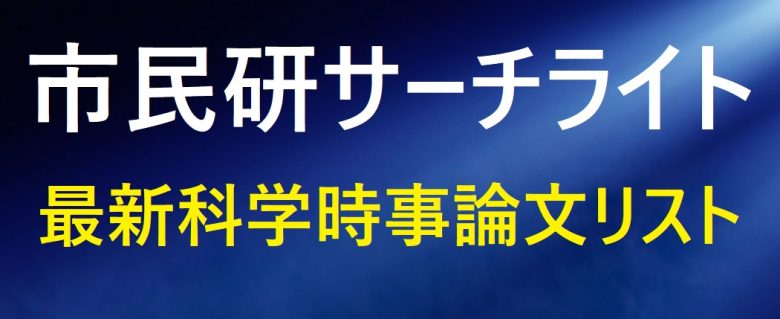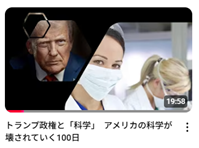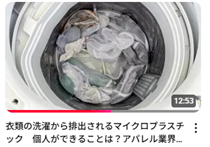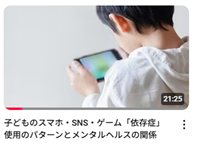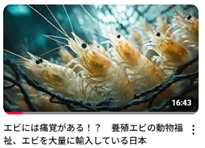市民研サーチライト 科学時事最新記事論文紹介
補遺(2) 2025年6,7月分
PDFはこちらから
上田昌文(市民研・代表)
▶毎週開いている「土曜広場」で、「市民研サーチライト」のなかから取り上げた記事論文を扱っています。
▶写真をクリックすれば「土曜広場」での解説がポッドキャストで再生できます(市民研YouTubeチャンネルにも掲載中)。
▶論文や資料へのリンクはすべて、この記事を掲載した『市民研通信』の発行時点で確認したものです。
▶この「補遺」の第1回分(2025年3,4,5月分)はこちらに掲載しています。
▶この「サーチライト」や「記事論文紹介」に関心をお持ちの方は、「土曜広場」にもオンラインでご参加いただければと思います。土曜広場の案内はこちらで行っています。
遺伝子編集の豚!? 日本にも「食肉」として流通が始まるか
CRISPR遺伝子編集ブタ、米FDAが承認 食肉として流通へ
従来品種改良によって行われてきた、特定の生物種に人間にとって都合の良い(味や収量や栄養面の向上で経済的利益を上げることにつながる)品質や機能を持たせることを、遺伝子組み換え技術ではなく、ゲノム編集技術で行うことが加速している。ブタのゲノム編集で狙われてきたのは、主に「ヒト疾患モデル」として利用できる(◆1)、あるいは、臓器の異種間移植のための、ブタの遺伝子改変だったが、今回のものは、病気に強いブタをゲノム編集で開発され、それをFDAが食用として承認し、来年にも米国市場に出回る可能性ある(◆2)、という話だ。日本での認可がいかなる形で進むことになるのかは、現在調査をすすめている。詳しい方はご連絡ください。
◆1:この目的で開発された「マイクロブタ」を中国では10年ほど前からペットとして販売されている。ゲノム編集ブタ、ペット販売へ
◆2:原著論文を含む詳しい情報はこちら:米国FDA, CRISPR-Cas9ゲノム編集を介してウイルス耐性が付与されたブタの販売を承認へ
トランプ政権と「科学」 アメリカの科学が壊されていく100日
Pennsylvania health advocates say Trump’s first 100 days in office have caused “100 harms” to local communities
気候技術プロジェクト、トランプ政権下の3カ月で80億ドル超が中止
Europe pledges €600 million to lure foreign researchers, vows to protect scientific freedom
U.S. scientists’ lives and careers are being upended. Here are five of their stories
「関税戦争」を筆頭にトランプ政権が疾風怒濤のごとく繰り出している政策は、米国の科学技術にも巨大な影響をもたらしている。特に目立つのは、大学行政への介入と補助金カットだ。これは、米国の有名大学が実施している多様性推進策(米国の各界で進められている「DEI:Diversity多様性、Equity公平性、Inclusion包括性」の一環)が過度にリベラル的であるとして敵視していることから来ている。この背景には、トランプを再選の勝利に導いた中間労働者層の支持(米国の「地殻変動」)がある(◆3)。科学界への激震を伝え、かつそれを批判するニュースや論評は『science』『nature』をはじめとする有力科学雑誌でも頻繁に掲載されている(◆4)。しかし、「地殻変動」と科学界に当然あってしかるべき発展基盤の体制とをどう折り合いをつけていくのかは見通せないままだ、と言えるのではないか。
◆3:NHK「ETV特集」(2025年7月19日放送)の「アメリカ 地殻変動の深層」が参考になる。
◆4:最新のものでは、例えば次の2本がある。
Trump order aims to politicize decisions on federal science grants(8月8日、science)
Cancelling mRNA studies is the highest irresponsibility(8月15日、nature)
「孤食」と「共食」についての医学的報告 健康、幸福度との関係
この記事の元になっているのは2025年版の『「世界幸福度報告書(World Happiness Report)」』だ。この報告書の「エグゼクティブサマリー」が公開されている(◆5)。」その第2章の「食事の共有は、社会的なつながりを測る指標の一部(ただし全てではない)と密接に関連しているようです。特に注目すべきは、人々が比較的多くの食事を共にする国では、社会的支援と肯定的な相互関係のレベルが高く、孤独感のレベルが低い傾向があることです。」に注目している。この報告の制作者の一人も登壇してなされたイベントでは改めて「人々がどのように料理をし、食事をするかということと、幸福感との関係についてはあまり研究されてこなかった」ことが指摘されている(◆6)。独居老人が増加している状況もふまえて、日本でこの問題の具体的改善を考究していく必要があるだろう(◆7)。
◆5:WHR 2025 | Chapter 1 Executive summary
◆6:食卓を囲むことは幸福の要因となるか?──World Happiness Report 2025が解き明かす「食」と幸福の科学的関係
AIのための巨大な「データセンター」のエネルギー消費と環境影響 電力、水、地域生活への影響
AIブームを支える「データセンター銀座」は砂漠地帯にあった
動画生成は別次元、思ったより深刻だったAIの電力問題
この問題を理解するには、そもそもデータセンターとは何をするところで、AIがどれくらい電力を消費することになるのか、といったあたりを知る必要がある(◆8)米国ほどの規模ではないにしても、また、関東と関西への集中という特異な傾向はあるものの、日本でも新設ラッシュが続いている(◆9)。「千葉ニュータウン」などの住宅地や、工業団地などが広がっている千葉県印西市では、隣の白井市にまたがるエリアに30余りのデータセンターが建ち並び、住民から住環境の悪化を懸念する声があがっている(◆10)。立地地域の景観の悪化、水の過剰な消費、ほとんど注目されていないが電力供給のための送電線から出る電磁波の問題など、AIのための無制限の電力の割当ての良し悪しという根本問題も含めて、大いに議論していく必要がある。現地取材も入れて調べてみたい。
◆8:生成AIによって電力は不足する? 安定供給に向けた対策とは
◆9:データセンターの現状と課題を徹底解説!最新の冷却技術や方法も紹介
◆10:千葉・印西市周辺 “データセンター銀座” 住民から懸念も 生成AI普及で建設相次ぐ
衣類の洗濯から排出されるマイクロプラスチック 個人ができることは? アパレル業界の将来は?
クローゼットから血液へ 衣類に潜むマイクロプラスチックの静かな危機
Release of synthetic microplastic plastic fibres from domestic washing machines: Effects of fabric type and washing conditions
マイクロプラスチックの放出源のひとつに、洗濯によって排出されるマイクロファイバーがあることは10年近く前からわかっていたが、その後いろいろな調査がなされ、合成繊維類を一度洗濯するだけで数百万ものマイクファイバーが放出されることさえあることも報告され(◆11)、全世界的にみてその半端ない排出量をどう抑えていくかが課題になっている。最も効果的な対策は、より優れた(自然素材を含めた)繊維製品の開発と普及にあることは明白だが、それがなかなか進まない。個々人が自宅でもできる対策もありはするが(◆12)、実行は難しいと感じる人が多いのではないか。そのなかで一つ注目されるのは「各家庭の洗濯機機へのフィルターの設置の義務付け」だ(◆13)。フランスでは2025年までにすべての新型洗濯機にフィルターを装備することを義務付ける法律が制定されており、オーストラリアでは 2030年までに業務用および家庭用の洗濯機にフィルターを装備することが義務付けられると発表された。日本も直ちにこの規制の制定に向かうべきだろう。
◆11:Plastic microfibers from household textile laundering: a critical review of their release and impact reduction や Microplastics in wastewater: microfiber emissions from common household laundry など
◆12:Washing instructions against microplastic pollution や Your laundry sheds tiny polluting plastic fibers. Here’s what to do. が挙げられる。
◆13:Laundry is a top source of microplastic pollution — but you can clean your clothes more sustainably
子どものスマホ・SNS・ゲーム「依存症」 使用のパターンとメンタルヘルスの関係
SNS・携帯電話・ビデオゲーム依存:単なるスクリーン時間ではなく、「依存的な使用パターン」が重要
Research on Smart Phone and Internet Addiction
この問題はおそらく大半の大人が思っている以上に深刻であり、思い切った対策が急務であると私は考えている。世界初の「16歳未満のSNS利用の禁止」(インスタ、TikTok、YouTubeも)に踏み切ろうとしているオーストラリアでは、政府機関がすでに2023年に『MANIFESTO FOR A BETTER CHILDREN’S INTERNET』という興味深い冊子を発行している(◆14)。子どもには「デジタル視聴」よりも楽しい・面白いと感じることのできる体験をさせることが要になると私は思うが、例えば、幼児期の「外遊び」の意義を改めて立証するような研究も出てきている(◆15)。ネットやIAへの過度の依存は、ヒトの学習能力や記憶力にもよろしくない影響を与えるのではないか、という疑いもあり、そうしたことの研究もなされている(◆16)。私は、リクエストに応じて、この「デジタル依存」の問題に関して講演を行ってきたが(◆17)、もし大人のみならず子どもたちを含めて皆で考え議論する場を設けてみたいと思う方には、講演内容の資料をお渡しできるので、連絡していただければと思う。
◆14:Manifesto for a Better Children’s Internet
◆15:『外遊びが幼児期のデジタル視聴による神経発達への影響を弱める』可能性を世界で初めて明らかに
◆16:Are the Internet and AI affecting our memory? What the science says
◆17:最近のものでは、こちらに報告されている、「府中・生活者ネットワーク」での講演がある(『わくわく通信』第188号)。
脳に蓄積するマイクロプラスチックとパーキンソン病の関係? 「プラスタミネーション」とは
「プラスタミネーション」とは何か?―マイクロ・ナノプラスチックとパーキンソン病の不気味な接点
Plastamination: A Rising Concern for Parkinson’s Disease
Plastamination(plastic + contamination:プラスチック+汚染)という言葉がわざわざ使われるようになったのは、マイクロプラスチックやナノプラスチックが生態系や生物系の隅々にまで浸透し、人体に全身的な健康影響をもたらすばかりか、水・大気・土壌の汚染をとおして動植物へのダメージをもたらし、ひいては食料安全保障にまで及ぶ、それこそ全地球的な問題になってきている、との認識が広まってきたからだ(◆18)。マイクロプラスチックの曝露・摂取・蓄積が中枢神経系に(認知症やパーキンソン病などを含めて)、あるいは、生殖腺にどう影響しているかに特に注目が集まっているが(◆19)、これらの研究が進んだとしても、リスクの評価と規制の導入は時間がかかるだろう。規制のないままでは生じてしまうだろう深刻な影響を、なんとか回避しなければならないのだが、その方策を私たちはまだ持てないでいる(◆20)。
※18:Plastamination: A One Health and Planetary Health Perspective on a Rising Global Crisis
※19:PLASTAMINATION: Outcomes on the Central Nervous System and Reproduction
※20:プラスチック環境汚染防止 国際条約とりまとめ 合意再び見送り
港にある危険な化学物質による「大惨事」のリスク
この『Chemistry World』のサイトに掲載された論考は非常に貴重なものだと思われる。近年の港湾での主だった「化学物質の惨事」を詳しく紹介し、一般の人々が思ってもみない港という場所で大惨事が起こる危険を知らせてくれるからだ。日本では2008年に、コンテナターミナルに保管されていた約10トンの硝酸が漏洩し発煙・発火に至る事故が発生したことがある(◆21)。また、大きな事故には至っていないが、一般的な危険物施設の流出事故数は少なくないようだ(◆22)。現在のところ、国際的なあるべき管理の指針を示しているのは2024年に出たOECDの報告書だと思われるが(◆23)、これに照らして、国(土木・海上・防災)・消防・労働安全・自治体など多層的な監督体制のもとになされているだろう日本の対策を、一渡りチェックしておく必要があるように思う。
◆21:特定化学物質による中毒(平成20年)
◆22:令和3年消防白書 2.流出事故
◆23:Management of hazardous substances in port areas
選挙とSNS ネット・スマホ時代の選挙はどうなるか
新聞はもとより、TVやPCよりもスマホでニュースを見ることの方がずっと多い―という傾向は若い世代ほど著しいのではないだろうか。しかも、その「ニュース」は報道局や記者が出したものよりも、SNSに投稿され拡散された短いメッセージだったり「切り取り動画」だったりするとすれば、「SNSを制するものが選挙を制する」という趨勢は否定しがたいものになる。この機会に、今回の参院選での参政党の躍進の背景に「SNSと投票行動」のどんな新しい事態がみてとれるか(◆24)、また、偽情報・誤情報がはびこりやすいのはなぜなのか(◆25)、対策の遅れが目立つ現状で、有権者は少なくとも何を心得ておくべきか(◆26)を、学んでおく必要がある。
◆25:“SNSのウソ情報 投票行動への影響懸念” 80%余 NHK世論調査
◆26:過熱するSNS選挙◆専門家に聞く「フェイクニュース」「切り抜き動画」との向き合い方
エビには痛覚がある!? 養殖エビの動物福祉、エビを大量に輸入している日本
The Lobbyists Fighting To Defend Animal Cruelty
タコやカニやエビにも苦痛の感覚がある、との認識のもとに、動物福祉に関連する法案の保護対象として、それらを「感覚をもつ動物」として追加していく動きは、じつは数年前から、いくつかの国で出始めている(例えば◆27)。エビで特に問題となるのは眼柄切除だが、世界がその廃止に向かって進み始めているなか(◆28)、日本でもASC認証(水産養殖の第三者認証)において基準を改善することが求められている(◆29)。養殖業最善慣行(BAP)認証を運営する世界水産物連盟(GSA)は8月27日、2030年末までに同認証でエビの眼柄除去の廃止を義務化すると発表した。日本もこれにならうことになるはずで、その正式な表明が注目される。水産業界における動物福祉の動向については、水産庁がまとめた資料(◆30)が参考になる。
◆28:エビの眼柄切除、世界で廃止が進む
◆29:エビ眼柄除去の廃止義務化 BAP認証、30年末までに
◆30:水産業界におけるアニマルウェルフェア(動物福祉)について
合成麻薬「フェンタニル」による危機 その背景と日本の状況
山岸敬和氏(南山大学国際教養学部国際教養学科教授)がこの問題をいち早く取り上げて、詳しい論評と解説を連載で書いている(◆31)。市民科学研究室の「TV科学番組を語り合う」で取り上げた「フランケンシュタインの誘惑:鎮痛剤 オピオイド・クライシス」(◆32)のなかでも扱われていた、オピオイド問題を深刻化させた「パーデュー・ファーマ」のことも山岸氏の連載の第5回で、そして6月25日の日本経済新聞のスクープ記事「米国へのフェンタニル密輸、日本経由か―中国組織が名古屋に拠点」についても第6回で、詳しく扱われている。この危機は収束に向かっているわけではまったくないことは、フェンタニルをはるかに上回る効力を持つとされる「ニタゼン類」と呼ばれる強力な合成オピオイドが欧州に流入し(大半は中国からの流入)、すでに数百人が死亡していることみてもわかる(◆33)。京都大学によってオピオイド鎮痛薬に代わる新薬の開発がなされ、有望な結果を得ているとの報道があり(◆34)、根本的な解決を図る方策の一つとして期待されるものの、日本での“拠点”の一蹴ができるのかどうか、その見通しはまだ得られていないようだ。
◆31:アメリカを揺さぶるオピオイド危機
◆32:「TV科学番組を語り合う」フランケンシュタインの誘惑「鎮痛剤 オピオイド・クライシス」