感染症のモデルが生まれる場所
~新著『予測がつくる社会』より~
日比野愛子 (弘前大学人文社会科学部、市民科学研究室科学コミュニケーションツール研究会)
PDFはこちらから
1. はじめに
私たちが何気なく暮らしている社会がいかにさまざまな見えない防御システムによって成り立っているかを、このたびの新型コロナウイルス感染症は突きつけることとなった。この記事を執筆している2020年5月の時点では緊急事態宣言も解除されはじめ、日本のムードはじょじょに日常のそれへと戻りつつある(そのような期待が満ちている)。とはいえ、流行の第2波、第3波に対する危惧も残っており、新たな防御システムを社会全体で構築していく試行錯誤の時間がしばらく続くといえよう。
まったくの偶然ではあるが、筆者は、2016年から2018年にかけて、感染症数理モデルが政策にどのように活用されているかに注目した研究を進めていた。日本で数名の研究者・関係者にインタビューを行うとともに、台湾でも話を聞くことができ、それぞれの国における数理モデル活用の実情の一端を知ることができた。今から振り返ると大変ホットな話題を扱っていたわけであるが、当時は、「感染症問題」も「数理モデル」も、きわめてマイナーな領域であり、台湾はともかく日本ではインタビューの対象者を探すのに一苦労するほどであった。とある機関を訪問した際にも、感染症にかかわる部門の表示の1つが地方創生へと上書きされていた場面が印象に残っている。この記事では、現在生じているコロナとモデルの問題を意識しながら、筆者が行った研究の紹介を行ってみたい。
2. 予測のダイナミズム
まず、筆者が上記の研究を進めるきっかけとなった科学社会学の研究プロジェクトを紹介させていただきたい。地震予測や経済予測など、私たちの社会は、未来についての何かしらの想定をもとに、現在の決定を下す行為に満ち溢れている。しかし、こうした未来の予測にもとづく意思決定はさまざまな問題もはらんでいる。1つは、予測の作成が多くの場合専門家の手に任せられ、ブラックボックス化されている問題である。また別の問題として、予測は、予測が表明されたことによって――その内容がどのようなものであっても――、予測を人々が信じることによって実現化してしまう自己成就の働きを持つ点が挙げられる。ただし、自己成就の過程でどういった関与者が影響力を持ち、どのような言葉や媒体によって予言が達成されていくかはよくわかっておらず、こうした過程に迫ることを研究プロジェクトではねらいとしていた。詳しい理論的背景や、具体的な事例(地震予測や経済予測等)の検討は、『予測がつくる社会:「科学の言葉」の使われ方』(山口・福島編、2019)にまとめられているので、ぜひご参照いただければ幸いである。
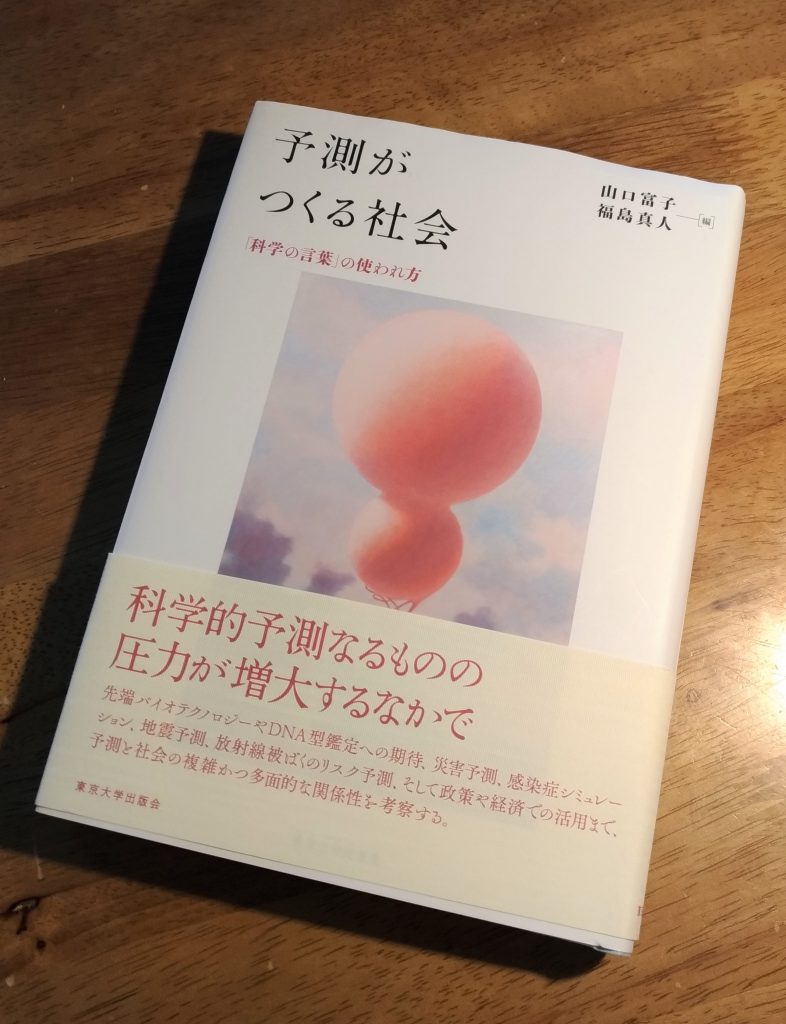
さてこの中で筆者が扱ったのが感染症課題である(前掲書第5章「感染症シミュレーションにみるモデルの生態学」)。感染症課題は、数ある社会課題の中でも数理モデル・シミュレーションを比較的適用しやすい領域であり、今後応用実践も進んでいくだろうと研究者コミュニティからは期待されている。「数理疫学」、「社会シミュレーション」が関連する領域であり、前者が、数理人口学によりつつ感染症そのものへの問題関心から成長してきた領域だとすれば、後者は、交通問題や防災時の避難行動などさまざまな人の動きを扱うモデル・シミュレーションの一つの応用課題として感染症を扱う。
コミュニティの側面からみると、感染症の数理モデルを扱う数理疫学、社会シミュレーションは、いずれも、どちらかといえばマイナーな位置づけに置かれてきた。数理疫学の研究グループとして国際的に名を馳せているのはイギリスのインペリアル・カレッジ・ロンドンであり、主に1つの研究室から研究者が育成されている。国内でも数理疫学を看板に掲げる研究室は1つ(北海道大学西浦研究室)といってよく、ディシプリンとしての専門家コミュニティはちょうど発達段階の状態にある。他方、社会シミュレーションに軸足をおく研究者コミュニティもそれほどボリュームは大きいとはいえず、コミュニティとしての活動も見えにくい。社会シミュレーションというくくりの中には交通から防災、ヘルスケアまでさまざまな研究対象が含まれる。さらに、これらシミュレーションは、何かの対象(A)についてのモデル・シミュレーションであるため、その対象(A)にかかわる学問領域(とその研究者)にハイライトがあたりやすいのである。
こうした特徴は、研究者のボリュームがそれなりにあり、研究対象とアプローチの対応もそれなりに系統立った中で、複数の研究室・研究者グループが互いに切磋琢磨するといった科学者コミュニティの特徴とは異なる。この点は、もしかしたら、感染症モデルと社会をめぐる一連の動きを理解する一助になるかもしれない。なお、横道にそれるかもしれないが、私がこのテーマに着手したのは、その前段階でシミュレーションの科学論に関する研究会に参加していたことも影響している。自然科学から、工学、社会科学までシミュレーションを実際に行っている異分野の研究者らと、科学史、科学哲学者が、シミュレーションとは何か、や、シミュレーションの意味・位置づけを議論する非常に刺激的な研究会であった。
さて、調査を進めるにつれ、確かに日本においては、数理モデル、シミュレーションの活用がそれほど進んではいない様子が明らかとなってきた。たとえば、インフルエンザの流行に学級閉鎖の時期がどれほど影響するのか、あるいは、病床数の管理や、年金問題など感染症課題のほかでもシミュレーションは助けとなる情報を提供するが、分析依頼はあっても、それが実際の政策にはなかなか活かされないという。科学の言葉が生み出す予言の力に踏み込むことがプロジェクトの目的であったわけであるが、モデルの言葉は、(当時)まだ日本社会に馴染んでいなかったのである。

3. 日本と台湾
東アジアでは感染症による影響も大きく、なにかしらモデルの活用が進んでいるのではないかと思い立ち、台湾でもヒアリングを進めた。現地の専門家に話を聞くと現場ならではの実態も分かってきた。実は台湾でも、以前は、感染症数理モデル、シミュレーションに対する関心は低かったのだという。状況が変わったのは、2009年のH1N1新型インフルエンザの流行による。当時は、どの機関においてもこうした新興感染症に対する情報がまったくなく、感染者がどのくらいのスピードで増えるのか、おさまるのか、あるいは、ワクチンやマスクの備蓄数はどのくらい必要か、といった情報が不足して混乱に陥った。感染症シミュレーションはこうした情報提供のニーズにこたえる有用なツールとして注目され始め、今では、政策関係者自身が数理モデル、シミュレーションを学びにくるほどであるという。
日本と台湾の聞き取り結果をもとに、筆者は、モデルの活用を、3つの局面からなるものとして整理していった。その3つとは、「モデルそのものの多様性の生成(どのようなモデルのバリエーションがあり、どの分野に使われているか)」、「データとモデルの相互依存性(どのようなデータが整備されており、そこからモデルがどう生まれるか。また、その充実にはどのような課題があるか)」、「モデルの受容(科学以外の関与者がどのようにモデルを導入するのか、しないのか)」である。ここではある種の生態学的な視点をとっており、モデルをなにかしらの生物に、データや社会的なシステムを、その生物が生息する環境のようなものと考えた上で、事例を見直していった。
結論を簡単に紹介すると、「モデルそのものの多様性の生成」、「データとモデルの相互依存性」に関して、日本と台湾には共通する点も多かったが、「モデルの受容」の局面で両者に違いが生じていた。そうした違いには、もちろん、意思決定の方法についての選好や、モデルを表示するインタフェース、また既存の防疫体制、歴史的経緯、そもそもの気候・風土など、さまざまな要因が関わっている。本記事で、取り上げたいポイントは、繰り返しになるが、感染症に関する数理モデルやシミュレーションという研究領域の若さである。研究コミュニティの発達段階や特質は、モデルそのものの社会的な受容のあり方と密接に絡み合っている。台湾では、政策関係者や公衆衛生関係者が、数理モデルを1年ほどで習得する教育プログラムに参加し、自身でモデルを使えるようになってきた。日本でも、北海道大学西浦研究室が感染症数理モデルの教育プログラムを精力的に展開してきたことは、数々のドキュメント資料が示している。しかし、意思決定を担う関係者と科学者が混合してモデル利用のコミュニティを形成してきた台湾と比べ、日本では、政策決定の責任者となる層(世代)と、研究実践に関与する層(世代)に乖離がある形となったのかもしれない。
4. 現在のコロナ問題に寄せて
つい数年前までは、影響力の弱さについて議論を展開できていた感染症数理モデルは、2020年の現在、その言葉の影響力の強さによって数々の論争を引き起こしている。「8割」などの数値が、数値の根拠や作られた経緯を外れて、一人歩きをしてしまっている。
数値の一人歩きについては、感染症に限らない問題である。私自身はデータを扱う社会調査法を教えている立場でもあり、こうした問題を非常に憂慮している。地道にリテラシーを上げる以外、どうするかといった答えも簡単には見つからず、対応が難しいように見える。1つの考え方として、数値化がやむなしとしても、数値化をする軸や、数値化を担う関与者を多元化することでバランスを取ることができるのではないか。コロナをめぐるコミュニケーションの混乱は、まだ、専門家コミュニティの組織化が未成熟な中で生じたことにも一因があるだろう。ただし、複数の軸によってバランスをとる動きはすでに日本の中でも生じつつあるように見える。
数理モデルやシミュレーションによる知の生産が埋没するでもなく、かといって過剰に信望されるでもなく、社会の防御システムを再構築していくことを願う。
文献
・山口富子、福島真人(2019)『予測がつくる社会:「科学の言葉」の使われ方』、東京大学出版会
・日比野愛子(2019)「感染症シミュレーションにみるモデルの生態学」、山口・福島編『予測がつくる社会:「科学の言葉」の使われ方』、東京大学出版会、113-138

「本記事で、取り上げたいポイントは、繰り返しになるが、感染症に関する数理モデルやシミュレーションという研究領域の若さである」の「若さ」とは,どういうことなのでしょうかね。
これから人数が増えていく人数が少ない段階にあるということ,それとも知見が未熟であるということ,あるいは,やればやるほどいろいろな本質的な疑問がでてくるという新鮮味に富んでいるということ?
あまり人々になじみがなかったという面が大きいものの,これだけ大きな社会問題となり,分野を越えた盛んな議論が一般メディアでも続きました。ある意味,知の総動員的状況になった成果はやはり大きいのではないか,そのなかで上で話題とされている学問は大いに意味をもったのでは,と私はそんな風にとらえています。「若さ」「一人歩き」がどんな弊害をもたらしたのでしょう?
「若さ」「一人歩き」といった抽象論に留まらない議論が重要なのでは?
私自身も地球科学をめぐる論考で,「若さ」に近い議論をしたことがあります。
『科学』編集部(林 衛分析):地震学を社会に生かすための条件,科学,1月号(2000)
「地球科学は,1970年代以降急速に進展している学問である」と書き出しました。過去の地震像,震源過程,プレートテクトニクスをとりいれた総合的な理解,活断層調査などによって,地震列島が具体的に生々しくわかってきているというような意味合いを前提とするためでした。
コロナウイルス禍を経たうえでの「若さ」問題の具体論をうかがいたいと思いました。