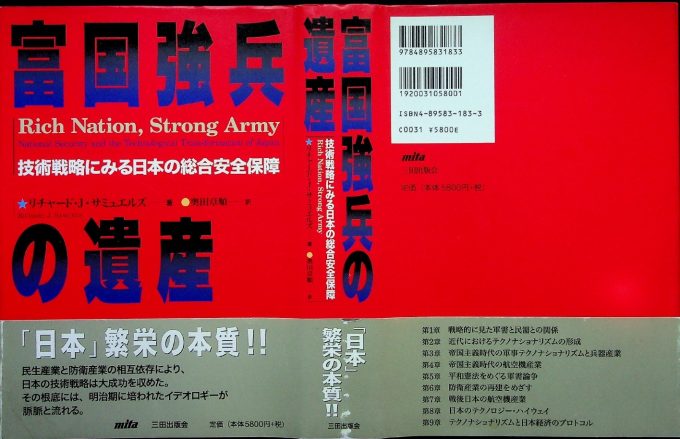リチャード・J・サミュエルズ著『富国強兵の遺産―技術戦略にみる日本の総合安全保障』
【連載】 開発主義政治再考 第4回
「富国」と「強兵」の関連性について、ないし社会インフラ論
山根伸洋(市民科学研究室会員)
全文PDFはこちらから
0.はじめに
第一次世界大戦を契機とした新しい国家統治の方法として、戦時動員を追求することを通じて彫琢されていった総力戦体制は、軍事へ政治や経済、市民社会を紐づけて徹底的に動員することを目的としていた。この総力戦体制としての国家の統治が、日本において少なくとも日中戦争から太平洋戦争、そして戦後の高度成長期まで継続する、という見立てが本稿を記述する立場だ。戦時社会を特徴づけるはずの戦時動員型の総力戦体制が、敗戦、占領改革を経た戦後日本において福祉国家として持続する[1]。この戦前から戦後にまたがって持続する総力戦体制の基盤には開発主義政治の持続があった。そして開発主義政治が戦前と戦後で持続するうえでの鎹(かすがい)の役割をリエンソールが提唱したTVA思想が担った。太平洋戦争の真最中の1943年にリリエンソールは『TVA-民主主義は進展する-』を刊行した。そして戦後、この本が日本において翻訳・紹介されることを通じ、改めてエネルギー開発を主軸とした地域開発の取り組みが、民主主義的政治体制とその下での豊かさの実現の象徴として受容されることになった。この一連の経緯を通じて、結果的に戦前から立案・構想されていた大規模河川開発事業は戦後に位置づけを変えて具体化されていくのである。
だが、リリエンソール自身が明らかとしているようにTVAの構想自体が第一次世界大戦のさなか、戦時動員体制の遺構を基礎として成立している。その点を踏まえれば開発主義政治は、戦時において効率的に人員や物資を動員することを目標とするし、第一次世界大戦以降、第二次世界大戦から冷戦期に至るまで、「平時」と言える時間を経験することなく連続する戦時のなかで開発主義政治もまた継続してきた(ないし北東アジアにおいては冷戦構造が持続しているので未だ持続している)。開発主義政治が持続する北東アジアにおいて、戦時から平時へ移行するための課題すなわち冷戦構造からの脱却のためには、開発主義政治のもとで総力戦体制と分かちがたく結びついてしまっている科学技術政策、福祉政策等を引き剥がし、自立化させていく歴史的総括作業が必要だろう。
つまり、あらゆる出来事が「結果的に戦時動員体制の構築に貢献する事象」として整理されていく学術的作業を積み上げること、その作業自体が戦時動員体制の維持への貢献となるので、そうした作業とは異なる総括が求められていると思われる。したがって戦時動員への貢献、軍需への貢献としての民需などの議論から民需の部門が自立化する契機の萌芽を19世紀以降の歴史過程の読み直しを行いながら見つけ出していく作業が必要になると思われる。まずは試みに日本近代の幕開けの政策を象徴するスローガンである富国強兵・殖産興業を再考するところから議論を続けていきたい。
1.富国強兵と殖産興業
サミュエルズは自著において技術とナショナリズムの結合について次のように説明する。即ち「技術は国家安全保障に欠かせないものとして位置づけられ、この考え方を支えるさまざまな信念や、それに基づいた行動が、「テクノナショナリズム」とも名付けられるべき考え方を形成していった。大日本帝国の指導者たちは何度も議論を重ね、ときには激しく意見を対立させながらも、軍事技術を国の基盤にする「軍事テクノナショナリズム」戦略に到達した。彼らはこの戦略が、経済を発展させると同時に国防力を高めると考えた[2]。」というものである。上記の文章はサミュエルズの著書『富国強兵』の「第2章 近代におけるテクノナショナリズムの形成」の冒頭のところにおける近代日本の技術と安全保障との関係についての考察の出だしに置かれた文章である。「テクノナショナリズム」から「軍事テクノナショナリズム」へ到達するとは一体いかなるものなのだろう。また軍事から距離のとられたテクノナショナリズムがありうるのであろうか、冒頭の文章に触れるとそうした疑問が喚起させられることになる。
明治期初頭に唱えられた「富国強兵」というスローガン、これはサミュエルズの著書のタイトルともなっているが、その原文は‘Rich Nation, Strong Army’であって富国と強兵は並置され相互に関連しあう四字熟語となっている[3]。サミュエルズも論じているように、明治期初頭以来の近代日本の歴史において富国と強兵との折り合いの付け方こそ大きな論点の一つであった。また19世紀における英国主導の世界市場構築のもとで強いられた近代国家形成の試みにおいて、富国としての産業政策と強兵としての軍事政策の両者において共通する課題として、欧米に由来する先進的科学技術の早期導入があったことは言うまでもない[4]。そして少なくとも幕末期の幕藩体制下においての科学技術政策は、国防のための欧米由来の技術の導入に力点が置かれていたと言える。欧米由来の科学技術の導入の当初は軍事技術として意識され、後に産業技術として一層強く意識されるようになったと言えるだろう。
実際に初代内務卿の大久保利通が殖産興業に関する建議[5]を行うのが明治7年(1874)のことであり、その翌年には内務省の殖産興業政策が位置づけられ具体化していく。軍事的要請にしたがい富国強兵を標榜した産業近代化政策から、あえて殖産興業という言葉を持ち出したことの内には、軍需とは異なる民需の要請が国家統治の基軸の一つとなるであろうという大久保の発想があった。実際に大久保は殖産興業の建議において、「大凡(おおよそ)国ノ強弱ハ人民ノ貧富ニ由リ、人民ノ貧富ハ物産ノ多寡(たか)ニ係ル」として「抑々(そもそも)国家人民ノ為メニ其責任アル者ハ、深ク省察念慮ヲ尽シ、工業物産ノ利ヨリ水陸運輸ノ便ニ至ルマデ総ジテ人民保護ノ緊要ニ属スルモノハ、宜シク国ノ風土習俗ニ応ジ民ノ性情知識ニ従ッテ其方法を制定シ、之ヲ以テ今日行政上ノ根軸ト為シ、其既ニ開成スルモノハ之ヲ保持シ、未ダ就緒(事にとりかかる、の意)ナラザルモノハ之ヲ誘導セザル可ラズ」として、地域それぞれの事情に寄り添いながら、産業を興し輸送と通信の便を計らなくてはならない、としている。大久保は、国家の統治者は「工業物産」すなわち産業政策から「水陸運輸ノ便」としての交通インフラの整備までを政治の基軸にすえて地域の実情に合わせて取り組まなくてはならないとする。この殖産興業の建議を基礎として、内務省の事業内容が翌年決定されていく。
ここで重要なことは、もちろん国家統治をめぐる軍事的な地域の制圧は当然のこととしても、それだけでは国家統治はままならないことを明確に指摘している点である。この点については大隈重信も『大隈伯昔日譚』[6]において、鉄道や電信の整備を画策していた当時の自身の思いを次のよう回想している。すなわち「四通八達の便を画り、運輸交通の発達を努めんには、鉄道を敷設し、且つ之れと同時に電信を架設して、全国の気脈を通ずること、実に最急の要務なり。而して是れただに運輸交通を便にするのみならず、其の封建の旧夢を破り、保守主義連、言換へれば攘夷家の迷想を開き、天下の耳目を新にして、『王政維新』の事業を大成するに少なからざる利益を与ふることならん」と述壊している。この一文は日本近代史を象徴する文句としてよく引用されているだけあって、示唆する内容もまた実に豊富である。この文章では、鉄道や電信の整備により、道路事情が悪く移動や輸送・通信の負担が大きい当時の日本の国内事情の改善がもたらされるばかりではなく、啓蒙の効果も期待でき、結果として明治維新政府に対する信認が増すといった内容が語られている。
つまり国家全域に鉄道や電信の人工物の技術ネットワークが埋め込まれていくことによって、その人工物が一種の文明化作用を及ぼすとしている点は注目に値する。即ち人工物を配置することで、その配置を基礎として形成される地域住民を含めた輸送・通信のネットワークが稼働し始めると、そこに組織化され係留される地域住民はみな「迷想が開」かれ「旧夢」から覚めるという見通しが述壊の中に含みこまれている。振り返ってみれば、幕末維新期以降の富国強兵・殖産興業政策の展開過程には、軍事に回収しきることができない、産業化・文明化・民需や民生といった論点が散りばめられていることが見て取れる。
[1] 例えば、『総力戦と現代化』(山之内靖、ヴィクター・コシュマン、成田龍一、1995、柏書房、p38)
編者の山之内靖は「方法的序論」において「総力戦時代が推し進めた合理化は、公生活のみならず、私生活も含めて、生活の全領域をシステム循環のなかに包摂する体制をもたらした。戦後日本に成立した憲法は民主主義の原理を高らかにうたいあげたという点で一つの頂点に達したといってよい。にもかかわらず、この民主主義は、戦時動員によってその軌道が敷かれたシステム社会化によってその内容を大幅に規定されていた。ここにおいて実現された福祉国家は、実のところ、戦争国家と等記号において繋がっているのである」と指摘している。本稿では、この指摘を踏まえて福祉国家=戦争国家の政治を開発主義政治としている。
[2] リチャード・J・サミュエルズ著『富国強兵の遺産―技術戦略にみる日本の総合安全保障』(1994=1997、奥田章順訳、三田出版会)p.69。
[3] 前掲書pp.70-72。サミュエルズは富国強兵という言葉の由来を中国の古典にまで遡っての説明を試み、幕藩体制期における日本の知識人(儒学者)たちが、その言葉をめぐってどのような議論が展開されたかについての考察を行っている。
[4] 飯田賢一「第1章 軍事工業と製鋼技術」、海野福寿編『技術の社会史3 西欧技術の移入と明治社会』(1982、有斐閣)pp.29-60。飯田は、韮山代官江川英龍の建議により建造された韮山反射炉の紹介より議論を開始する。そして「技術近代化の発端が軍事的要請に負うことは、近代日本の大きな特質である」としている。
[5] 『日本近代思想体系8 経済構想』(1988、中村政則・石井寛治・春日豊 校注、岩波書店)pp.16-19。
[6] 『明治史資料大隈伯昔日譚』(1938、大隈重信述・円城寺清著・京口元吉校註、富山房)pp.351-352。
【続きは上記PDFでお読み下さい】
市民科学研究室の活動は皆様からのご支援で成り立っています。『市民研通信』の記事論文の執筆や発行も同様です。もしこの記事や論文を興味深いと感じていただけるのであれば、ぜひ以下のサイトからワンコイン(100円)でのカンパをお願いします。小さな力が集まって世の中を変えていく確かな力となる―そんな営みの一歩だと思っていただければありがたいです。