【連載】 開発主義政治再考 第5回
補論/田園都市国家ないし国家の空間的実践をめぐって
山根伸洋(市民科学研究室会員)
連載第1回はこちら
連載第2回はこちら
連載第3回はこちら
連載第4回はこちら
全文PDFはこちらから
1970年代末、全国総合開発計画(以下、全総)から日本列島改造論にいたる高度経済成 長政策、そして国家的メガイベントである1964年開催の東京オリンピックから1970年大阪万国博覧会にいたる開発主義政治全盛の時代を踏んで、「オイルショックを契機」とする反省と見直しの時代に入るのが1970 年代の半ば以降の一般的な経済動向に対する理解だろう。2010年代の安倍政権の時代において、2011年3月11日の東日本大震災からの「復興」 を象徴する国家的メガイベントとして、2020年東京オリンピックならびに2025年大阪・関西万国博の開催が決定された。この経緯から読み取れることは、1960年代の全総から新全国総合開発計画(以下、新全総)そして日本列島改造論に至る時代を「成功経験」として位置づけ、その時代への「憧憬」を動員・組織化することで、2010年代の東日本大震災からの「復興」を成し遂げようという強い願望がそこに込められていたということであろう。だが、必ずしも市民的に共有されているわけではない歴史的記憶の参照を強いるような国家的メガイベント、その開催をもって「経済成長」の実現が達成されつつあるといった演出がなされるとしたら、東日本大震災の復興をめぐる諸課題の現実へ誠実に向き合うことへの妨げとなる危険性がある。と同時に、戦後の高度成長期に顕現する様々な開発主義政治の矛盾[1]の忘却と、ある種の「成功経験」の語りの横行を許してしまうことになりかねないのではないだろうか。
2021年の秋口には一層深刻化するコロナ禍において、新しい資本主義を標榜する政権が誕生する。この政権は「新自由主義」的社会・経済政策の修正を前提として、新たな 資本主義を構想するとして、その中で、「デジタル田園都市国家構想」が語られていくことになる。実はこの新政権、池田内閣の所得倍増計画に倣い所得の倍増を唱えようと試み、戦後日本の開発主義政治の時代の記憶を選択的かつ強引に参照する傾向にあった。さすがに1964年の池田内閣の政治的文言の参照は思いとどまったようだが、「デジタル」というやや意味不明な冠を除いた「田園都市国家構想」は、1970年代末の大平政権下で構想された一定の議論の蓄積のある国家構想であった[2]。

1970年代半ば、とくにオイルショック以降の東西冷戦下の米国が軸となった西側世界においては、戦後復興を支えた開発主義政治への反省をめぐる言説が流行していた。例えば「成長の限界」をめぐる議論であり、大量生産・大量消費への疑問の提示など、ないし開発 様式の転換、とりわけ、都市空間を生産実践の現場から消費実践の現場へ転換させる「再開発」[3]を促す議論が出来し始めた時期でもあった。そして来るべき未来像として「情報化社会」[4]の到来が語られた。こうした時代状況に応じて、第三次全国総合開発計画(以下、三全総)が1977 年11月に福田赳夫内閣において閣議決定される。この新しい総合開発計画では、全総(1962年)および新全総(1969年)について「第二次全国総合開発計画(新全 国総合開発計画のこと、引用者)においては、第一次全国総合開発計画における拠点開発方式を更に充実させ、中枢管理機能の集積と物的流通の機構とを体系化するため、全国的なネットワークを整備し、この新ネットワークに関連せしめながら各地域の特性を生かした自主的、効率的な大規模開発プロジェクトを計画し、これを実施することによって、その地域が飛躍的に発展し、漸次その効果が全国土に及び、全国土の利用が均衡のとれたものなるという方式」として説明している。しかしこの時期の開発構想では、相対的には人々の暮らしぶりの組み立てすなわち「生活圏」の構想立案やその実施に向けた取り組みに遅れがあった点が率直に言及されており、その意味でこれまでの開発主義政治への反省[5]として位置づけられてきた。この生活圏の構想の中身をめぐる議論が、1970年代後半、大平総理の政策研 究会において議論されることになる。主として、「人間居住の総合的環境の形成」という課題に応答する新しい国土・国家構想が求められることになった。
大平総理の政策研究会は九つの研究グループより構成されており、1980年には各々の研究グループごとに報告書が刊行された。そして、「田園都市構想研究グループ」が提示した未来国家構想が「田園都市国家」であった。およそ40年前に構想された国家構想に「デジタル」という言葉を冠して再度「デジタル田園都市国家構想」が打ち出されたことの背景には、2010年代を1960年代に模した新自由主義的経済成長の時代として位置づけて、2020年代を1970年代に模して、行き過ぎた成長戦略への反省と地域社会における生活の豊かさの追求の時代として押し出そうという意図があるのであろうか? やや唐突ともいえるこうした新しい国家構想の押し出しの背景事情を把握するために、大平総理の政策研究会報告書の関連部分について若干の説明をしていきたい。
1980年刊行の『大平総理の政策研究会報告書-2 田園都市国家の構想―田園都市構想研究グループ―』(内閣官房内閣審議室分室編、1980、大蔵省印刷局)は、議長を梅棹忠夫氏が務め、香山健一氏(以下敬称略)、山崎正和氏など錚々たるメンバーによって構成されていた。本報告書の紹介と分析は別稿に譲りたいが、そこで明示されている時代認識は次の通り。
「われわれの構想する田園都市国家は、19世紀末から20世紀初頭にかけて西欧諸国において構想され、実験された田園都市モデルの理念や経験に学びつつも、その後の人類の欲求の高度化、多様化とこれに応える科学技術の進展、数々の歴史的経験を踏まえ、日本文化の特質を生かしつつ、脱工業文明への転換に対応する創造的なものでなくてはならない。」[6]
西欧由来の社会モデルを基礎としながら、時代の転換に当たって、日本ないしアジアに独自の展開を展望していく内容となっていた。また他の研究グループの報告書では、脱工業文明の時代を文化の時代として、「近代化」を達成し、高度産業社会の仲間入りを果たした1980年代の日本の行方を「近代を超える時代」への対応として課題化している。およそ40年前、ちょうどバブル景気に突入する直前の時代を理解するうえで大変に興味深い報告書だろう。
だが、なぜ改めてこの時代の報告書のアイデアなり構想が参照されているのだろうか。
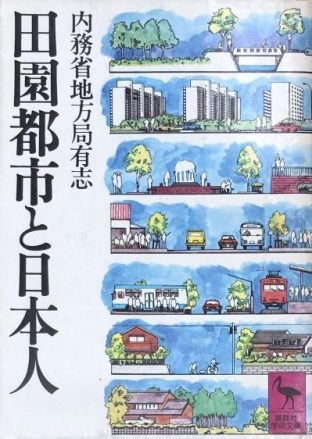
1980年4月に、田園都市構想研究グループの主要構成メンバーであった香山は、内務省地方局有志を編者とする『田園都市と日本人』という書籍(講談社学術文庫)を刊行する。これは日露戦争後の1907年に博文館より刊行された『田園都市』を再録したものと香山は前書きで説明する。そして当該期における内務省官吏の海外における活動について、とりわけ国際都市計画会議等への参加などを紹介しながら、欧米へのキャッチアップの時代から欧米とともに歩む時代への転換をよく示す文献として紹介している。そして前文「田園都市 国家への道」の最後を次の文章で締めくくる。
「二十一世紀への日本の長期国家目標は何かと問われるならば、私ははっきりと、それは軍事大国の道でもなければ海外膨張への道でもない。美しい自然と人工の調和、あたたかい人間関係、豊かで、自由で、多様な文化に彩られた「日本型田園都市国家」の成熟であってほしいと答えたい。この道こそ、日本人と日本文化の特質にもっとも相応しい道であり、脱工業化社会への世界 史的移行過程での日本の先導的試行の道である。そして、その道は、模倣のなかにではなく、近代を超える新しい国家システムの創造の中にしかないのである。」[7]
21世紀をおよそ10年過ごすうちに東日本大震災に見舞われ、その復興の文脈に戦後復興から高度成長期の歴史的経験を重ね合わせたのであろうか。東西冷戦期以降、グローバル化の時代、そしてそれに付随した新自由主義的改革政治がもたらした日本社会の変化についての分析は未だ途上にあると言えるが、その矛盾を糊塗隠ぺいするかのように、戦後日本社会の記憶のリソースが、やや安直に参照され過ぎていないだろうか。ないし、その参照にはなんらかの思惑があるのだろうか。読み手に拙速の印象を与えてしまいかねないきらいがある。
いずれにしてもグローバルな世界秩序を構成してきた地球環境問題をめぐる言説が脱炭素による温暖化の抑制に定まってきている現段階において、地域ごとに社会基盤に関連する諸政策、例えばエネルギー政策等での偏差が生じてきている。その中で、改めて、都市・地 域・国土・国家を超える地域といった空間的単位・概念が重要な意味をもち始めている。1970年代、東西冷戦下の西側世界、主としてフランスの国家的動態を参照することで自らの理論を鍛え上げていったアンリ・ルフェーブルは1974年に空間概念を積極的に援用することで、理論的主著とも言うべき大著『空間の生産』を刊行する。本書においてルフェーブルは地理的属性に基づく差異を解読するために空間概念を積極的に導入し、空間的実践を「社会的実践のあらゆる局面・要素・契機をたがいに切り離すことによってそれらを空間的分野へと投影することにほかならない」として空間的実践を社会の管理に関連するものとする。そのうえで、「空間の科学」を、知の政治的利用とし、その政治的利用を隠蔽するイデオロギーを伴うものとし、さらに、科学技術のユートピアを表現している。その科学技術のユートピアのうちには、空間に関するあらゆる種類の構想として建築、都市計画、社会計画の構想が 含まれるとしている[8]。また、国家について、ないし地方経営について、次のような説明を与えている。「今日では、国家と国家機構(官僚主義的・政治的な機構)は空間にたえず介入しており、空間を道具として利用して、経済的領域のあらゆるレベルに介入している。」「国家のレベルで思考し行動するものだけが、地域と地方の整備に精通し、フローとネットワークに精通している」[9]。空間と表象の概念を導入することによって、生産概念を耕すことに成功し、多次元の空間記述を可能としたルフェーブルの社会学的構想力が開花するのは、やはり1970年代半ばとなる。ダニエル・ベルが発見する資本主義の新たなる展開と同様にルフェーブルも空間概念を媒介として多層化していく市場空間の展開を想像しえたのではないだろうか。しかしルフェーブルの指摘、空間的実践における国家の介入をめぐる事態は重要な指摘だろう。恐らく、新たな国家構想が呼号される際には、その構想の内実もさることながら、国家の空間的実践に付随して生じる多様な次元における力のかかり具合を注意深く見極め、生活者の目線から測定していく術を見出していかなくてはならないだろう。
翻って現在、あらためて1970年代に育まれた構想や知の枠組みの参照が求められているのであれば、そこにいかなる時代的相同性があるか冷静に見定めていく必要ある。欧米社会の模倣ではない新たな方向性、新たな時代の扉をこじ開けたいという欲求が社会的に高まっているのであろうか。それとも参照すべき先進社会の政策モデルを見出せない現状でのある種の喪失感の社会的蔓延の裏返し的な表明なのであろうか。いずれにしても私たちは空間的差異に立脚したアジア地域に根差した新たな時代とそれに見合う社会構想を見出していかなくてはならないのだろう。冷戦構造が持続し分断国家が継続するアジアにおいて切望される、ポスト冷戦期の到来は、おのずと欧米とは異なる道筋をたどることになるだろう。その際にもっとも注意深くなるべきは、欧米由来でありながらも独自の軌道をたどりつつある科学技術の動向、そして、それに立脚した企業や国家の動態であろう。その観点も含め今後の「デジタル田園都市国家構想」 の
成り行きに注目してきたい。
[1] 例えば、『夢の島 公害からみた日本研究』(本間義人、黒岩徹訳、ノリ・ハドル、マイケル・ライシュ、ナハーム・スティスキン著、1975、サイマル出版会)。本書の扉には「外国人は公害先進国日本の経験から何を学ぼうとしているのか!」と銘記されている。1970 年代、ちょうど大阪万博終了後の日本の実況を見聞した外国人留学生たちのルポルタージュに触れれば、この時代が示している矛盾に震撼せざるをえない。
[2] 「大平総理の政策研究会報告書」については、小渕政権(1998 年から 1999 年)のもとでの「21 世紀日本の構想」懇談会においても高く評価された。この報告書の内容が再評価される時期がどのような時期なのか、時代的考察の必要性を認識している。
[3] 都市臨海部の生産・流通機能の移転に伴う臨海部再開発。東京湾、湾岸エリアの高層住 宅とそれに付随するアメニティの設置など。80 年代後半より世界各所の大都市において観察された。
[4] この時代を代表する文献の一つに『資本主義の文化的矛盾』(林雄二郎訳、ダニエル・ベル著、1976=1977、講談社)がある。何よりも本書において、19 世紀における市場経済 に対して、20世紀の市場経済を「新資本主義」と銘打ち、その脆弱性を言い当てた点、そして 1920 年代に始まる大量生産・大量消費の時代の 1970 年代における終焉を宣言し(これは都市開発の基調を生産都市から消費都市へ切り替えるきっかけともなる)、さらには脱産業化社会の到来を宣言してアメリカの動揺を指摘していることを思い起こす必要がある。
[5] 『国土計画を考える 開発路線のゆくえ』(本間義人、1999、中央公論新社)。本書 p.102「三全総とは何だったのか」において、これまでの開発計画の反省に立って「計画の主眼が経済の効率性、合理性を追求するところに置かれていたのに対し、水系に沿った定住圏を配置し、上下流を一体化した地域で居住環境を総合的に整備しようとした」点、そしてその主体を「市町村」としたことをもって、「それまでの工業先導、国家管理型の国土開開発にくらべると、大きな発想の転換」という評価を与えている。
[6] 『大平総理の政策研究会報告書-2 田園都市国家の構想―田園都市構想研究グループ―』pp.7-8。
[7] 『田園都市と日本人』(内務省地方局有志、1980、講談社)p.8。
[8] 『空間の生産』(アンリ・ルフェーブル、齋藤日出治訳、1974=2000、青木書店)pp.43-44。
[9] 前掲書p.542。
市民科学研究室の活動は皆様からのご支援で成り立っています。『市民研通信』の記事論文の執筆や発行も同様です。もしこの記事や論文を興味深いと感じていただけるのであれば、ぜひ以下のサイトからワンコイン(100円)でのカンパをお願いします。小さな力が集まって世の中を変えていく確かな力となる―そんな営みの一歩だと思っていただければありがたいです。
